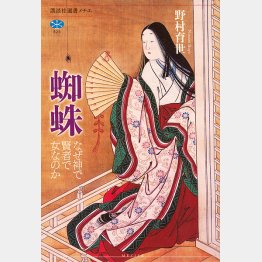「蜘蛛 なぜ神で賢者で女なのか」野村育世著
「蜘蛛 なぜ神で賢者で女なのか」野村育世著
虫は好きだけど蜘蛛だけは嫌いだという人が結構いる。それが高じてアラクノフォビア(蜘蛛恐怖症)になる人もいるという。この蜘蛛への忌避感は古今東西共通しているものなのだろうか。そうではない、と大の蜘蛛好きを自任する著者はいう。ギリシャ、北米、アフリカ、アイヌなど、世界の神話や遺跡には蜘蛛がしばしば登場し、創造神、賢者として描かれることも多い。日本でも弥生時代の銅鐸に蜘蛛が描かれている。また、糸を紡ぎ、織る作業が女性労働だったため、蜘蛛と女性のイメージが結びつくことも世界各地で見受けられる。そのように身近な存在で親しまれてもいた蜘蛛が、なぜ嫌われる存在となってしまったのか? 本書は、古来の日本人と蜘蛛との関わりをたどりながらその謎に迫っていく。
古代の日本では夫が妻のもとに通う妻問婚が一般的で、夫(恋人)を待つ女性は蜘蛛が網を張るのをいとしい人が来る吉兆と考えていた。「日本書紀」の衣通郎姫の歌をはじめ、蜘蛛のふるまいを見て相手が来るか来ないかを占う歌が多く歌われている。また、清少納言は蜘蛛の巣に露が宿った様子を「あはれ、をかし」と愛でているように、王朝貴族の美意識に蜘蛛は欠かせないものだった。そのほか、神や仏の使いとしての蜘蛛の伝承も数多く残されている。それが鎌倉時代以降になると妖怪や化け物としての蜘蛛が現れるようになる。
これは13世紀に成立したとされる「虫めづる姫君」がすでに虫好きが変わり者とされるように、この時代に「蜘蛛だけでなく、人間以外の生きもの全般に対するまなざしの転換が起こった」と考えられ、「それは、人間の中でもマイノリティーの異国人や、女性に対するまなざしの変化とも連動している」と、著者はいう。
この指摘は、異形・特殊なものを排除・敵視する風潮が広まりつつある現代日本にも真っすぐに突き刺さってくる。 〈狸〉
(講談社 2970円)