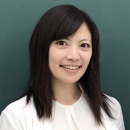【もち麦】血糖値と腸内環境の改善で再評価…ごはんやスープに混ぜて食べたい
日本では弥生時代の遺跡からも出土している大麦は、古くから米と並ぶ主食作物でした。特に江戸時代には、夏場の体調不良を防ぐ「麦飯」が奨励されていたので、武士から庶民まで広く食されていた記録があります。ただし、戦後の食糧事情改善とともに「白米=豊かさ」の意識が広まり、日常食としての大麦は次第に姿を消していったといわれます。もち麦はそんな大麦の一種です。
近年、もち麦が再び注目される背景には、食後血糖値や腸内環境に関する明確な科学的根拠が増えてきたことがあります。β-グルカンは腸内で水分を吸収してゲル状になり、小腸での糖吸収速度を緩やかにする働きがあるのですが、白米にもち麦を50%混ぜた食事を4週間摂取した群で食後血糖値のピークが有意に低下し、食後インスリン分泌も抑制されたと報告されています。
また、もち麦を1日50~80グラム摂取した被験者において、腸内のビフィズス菌および酪酸産生菌が増加し、便通の改善や腹部の張りの軽減が認められているのです。酪酸をはじめとする短鎖脂肪酸は、大腸の上皮細胞の主要なエネルギー源なので、腸粘膜の修復とバリアー機能維持に関係することが知られています。