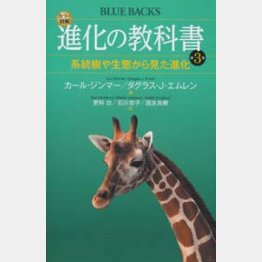動物も人も群れをつくることには意味がある
「進化の教科書」カール・ジンマー、ダグラス・J・エムレン著 更科功、石川牧子、国友良樹訳/講談社ブルーバックス
講談社ブルーバックスには、理科系の専門教育を受けていない人でも最新の自然科学や技術を理解できるように説明している優れた本が多い。本書もそのひとつだ。高校の生物教科書では知ることができない進化に関する最新理論を学ぶことができる。群れをつくる動物の生態が興味深い。
<アデリーペンギンは南極の沿岸部に生息する。アデリーペンギンを見ると、群れを作ることによって、捕食から逃れていることがわかる。ペンギンは魚を探すために、氷の上から海へ飛び込む。そのときに、ちょうど近くを泳いでいたヒョウアザラシに食べられてしまうことがある。そのため、1羽で飛び込むのではなく、何百羽もの群れになって、いっせいに飛び込む。ヒョウアザラシはアデリーペンギンの数に圧倒されて、1羽に的を絞れなくなる。もちろん個体数が多いことで、希釈効果も生じている。大勢で飛び込むことで、1羽1羽のアデリーペンギンが食べられる可能性は低くなるのだ。>
確かに合理的な説明だ。餌を取るためにも群れをつくることが有利な場合がある。
<群れを作ることで利益を得ているのは、捕食者も同じである。ミクソコックス・クサントゥスでは、1匹で餌となる細菌を襲うよりも、群れをなして襲いかかった方が効果的である。ライオンやイルカやオオカミやハイエナも、群れで効率的な狩りをする。アメリカシロペリカンは群れになって水をたたき、魚集めをおこなう。そして、浅いところに集まってきた魚を、嘴ですくい取るのだ。この場合も、1羽で魚を探すよりも群れで魚を集める方が、多くの魚を食べることができるようだ。>
動物の行動を軽々に人間に当てはめてはいけないことはよくわかるが、文科系人間の評者の場合、どうしても現実の人間社会との類比で考えてしまう。1人で働くことよりも会社をつくることの方が、自分を守るという観点からも、収入(餌)を得るという観点からも有利なのである。人間は群れをつくる動物であることを忘れてはならない。いま勤めている会社に不満があるとしても、群れから離れて独立するなどという発想は、軽々に持たない方がいいと思う。 ★★★(選者・佐藤優)
(2017年9月1日脱稿)