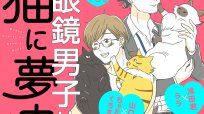判定はたったの3秒! 食品添加物の量がすぐに分かる「AIアプリ」を使ってみた

リモートワークの普及もあって、手軽においしく食べられる加工食品は生活になくてはならないものとなった。その代表格はカップ麺や冷凍食品だが、これら加工食品には食品添加物が使用されているため、安全かどうか不安に思っている人は多いだろう。すぐに添加物の有無を確認できるツールがあれば便利…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,437文字/全文2,578文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。