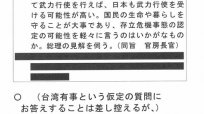「緊急事態条項」新設案の自己矛盾 “改憲”が目的化しているのではないか

「緊急事態条項」とは、戦争や大きな自然災害といった国家存亡の機に際して、権力分立と人権尊重を保障した憲法を一時停止して、首相に国家の全権を集中して効率的に国家の生き残りを図る、憲法の例外条項である。理論的には筋が通っており、他国にも先例はある。
憲法は本来、国家権力の乱用…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り831文字/全文972文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。