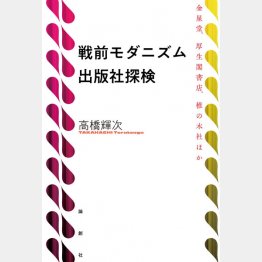「戦前モダニズム出版社探検」高橋輝次著
「戦前モダニズム出版社探検」高橋輝次著
1960年代末から80年代にかけて、異端・幻想文学を領導し、澁澤(龍彦)・種村と並び称されたドイツ文学者の種村季弘が亡くなったのは2004年。没後20年の昨年には「種村季弘コレクション 驚異の函」(ちくま学芸文庫)、「種村季弘・異端断片集 綺想の美術廻廊」(芸術新聞社)の2冊が刊行、「種村季弘没後二十年 綺想の美術廻廊」という展覧会も開催された。久々にその名前に出会って懐かしんでいたら、本書冒頭に「種村季弘の編集者時代──光文社での三年間を追って」という1章が置かれているのが目に留まった。
著者は種村が書いたエッセーそのほかから3年ほどの新米編集者時代をたどっていく。その中で種村が新宿の文壇バー「カヌー」のマダム、関根庸子が書いたベストセラー小説の編集者だったという一節を見つける。調べてみるとマダムはその後、森泉笙子という名前で「新宿の夜はキャラ色」というバー時代の思い出をつづった本を出している。著者は早速その本を古書店で入手。そこには種村も含めて、三島由紀夫、大岡昇平、武田泰淳、埴谷雄高、梶山季之といった面々が登場し、貴重なエピソードが書かれていた。
だいぶ遠回りをしたが、本書は表題にある通り、大正末期から昭和初期にかけてモダニズム文学を牽引した出版社のうち、金星堂、厚生閣書店、椎の木社の3社を中心に取り上げている。といっても整序された叙述ではなく、ある文章の一節を手掛かりに何本かの糸をたぐり寄せ、いくつもの寄り道しながら当初意図していた場所とは別の場所へ行き着くこともしばしば。また肝心の資料を入手したくとも高価で手が出ないことも多い。そういう場合は各種文学館に該当箇所のコピーを頼むことに。狙った資料に行き当たるまでの経緯はまさに「探検」だ。近代文学史の貴重な補助線を提供するとともに、古本好きの独特の生態も余すところなく描かれている。 〈狸〉
(論創社 3300円)