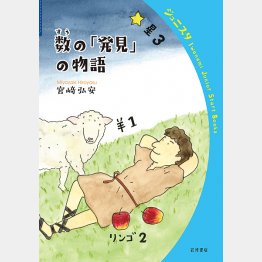「数の『発見』の物語」宮﨑弘安著
「数の『発見』の物語」宮﨑弘安著
世に算数や数学がわからなくて、嫌いになってしまう人が結構いる。ことに、小学校では「分数」、中学校では「負の数」に悩まされることが多いようだ。スタジオジブリの「おもひでぽろぽろ」でも、主人公のタエ子が分数を分数で割ることの意味がわからないといって姉につっかかるという印象的なシーンがあった。
しかし、これら学校で習ういろいろな「数」たちは、昔の学者たちが頭を悩ませながら「発見」したもので、発見当初はその数を認める派と認めない派とで論争になったりもした。本書はそうした「数」たちがどのように発見され、一般に使われるようになったかを物語風に語ったもの。
まずは自然数の発見。古代の人があるものの個数を数えるために、対象物の異同によらず個数という情報を抽象化したものが自然数だ。その次の発見は0。発見したのは7世紀初頭のインドの数学者。この発見によって位取り記数法という便利な自然数の表し方が可能になったのだが、無というものは存在しないと考えていた古代ギリシャやその影響を受けたヨーロッパの数学者は0という数をなかなか受け入れることができなかった。
そして「負の数」。0から1を引いたときに出てくるのが-1。ここまではわかる。しかし、(-1)×(-1)=1。なぜマイナスにマイナスをかけるとプラスになるのか。タエ子のようにつっ込みを入れたくなるが、本書ではその理由を丁寧に説明してくれる。こんな具合に、素数、無理数、虚数、複素数といった難解な「数」たちについて解き明かしていく。
本書はジュニア向けに書かれたものだが、かつて算数・数学に挫折した元ジュニア、あるいは現在悩みを抱えているジュニアを子に持つ親たちも十分楽しめる。なにより、法則や数式でがんじがらめのように思えた数学が意外に自由な学問であることを知ることができたのは楽しい。 〈狸〉
(岩波書店 1595円)