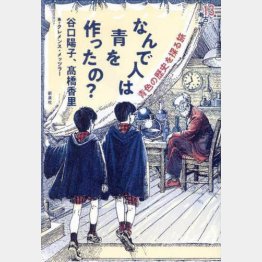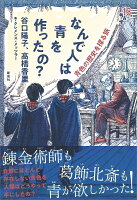「なんで人は青を作ったの?」谷口陽子、髙橋香里著 クレメンス・メッツラー絵
「なんで人は青を作ったの?」谷口陽子、髙橋香里著 クレメンス・メッツラー絵
青い色は現代ではごくありふれたものとして日常生活に取り込まれているが、その歴史は意外に新しい。ヨーロッパで青が愛用されるようになるのは中世以降で、古代日本の「青」は緑色も指していて、いわゆるブルーは藍染めの色で、これが庶民の間で広まるのは藍染めの布が普及した江戸時代以降のこと。また、自然にはほとんど存在しない青を人工的に作るにはさまざまな苦労があった。本書は、中学生の少年2人が色の専門学者に導かれながら、歴史上の青の再現実験をしていく過程を描いたもの。
夏休みに入った中学1年生の蒼太郎は友人の律を誘って森井老人が主催する上野の科学倶楽部に通っている。小学生から高校生まで20人くらいが集まるいろいろな実験をする理科実験教室だ。蒼太郎たちが託されたのは、人類がどうやって青色を手にしたかの実験の手伝い。古代エジプトではアフガニスタンでしか採取されなかった貴重な石、ラピスラズリを青色顔料としていたが、その顔料1グラムと金1グラムが同価という貴重品。ティツィアーノやフェルメールらがラピスラズリから作ったウルトラマリンブルーで絵を描いたことが知られている。もっと安価なものとして発明されたのが酢と銅から作られたヴェルディグリ。しかし、これは変色しやすかった。安価かつ質の良いものとして18世初頭のドイツに登場したのがプルシアンブルーだ。牛の血液などを原料にしたこの顔料は日本にも輸入される。ベロ藍とよばれたこの青は、葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」の波にも使われるなど、浮世絵師たちに愛用された。
そのほか、オドントライト、スマルト、エジプシャンブルー、マヤブルーなどの青の顔料が登場するが、本書がユニークなのはそれらの顔料を作る実験を通じて、主人公たちが昔の人たちの苦労の一端を体験していくことだ。〈13歳からの考古学シリーズ〉の一冊。 〈狸〉
(新泉社 2420円)