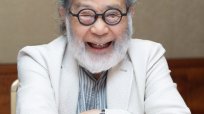日用品の「日本製回帰」がインフレ本格化で進行中 国内で作ったほうが安い状況に

1ドル=130円に乗せるなど急激な円安に加え、原材料費や物流費、人件費の高騰で、輸入に依存してきた日本の日用品は値上げを余儀なくされている。その代表が100円ショップで、低価格・ワンプライスがいよいよ成り立たなくなってきた。
「ダイソー」運営の最大手・大創産業では、300…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り819文字/全文960文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。