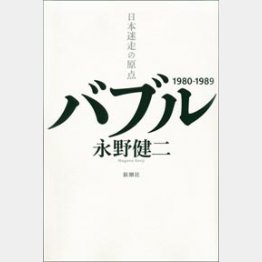バブルの主役たちがどう行動したか生き生き伝わってくる
「バブル 日本迷走の原点」永野健二著/新潮社
私がライフワークにしている研究は、「人はなぜ狂うのか」ということだ。だから、自分自身でも「バブルとデフレ」という本を書いているし、これまでバブルに関して書かれた本をたくさん読んできた。そうした本のなかで、本書は異色の作品だ。
それは、著者がバブル期に日本経済新聞の記者として、実際にバブルの主役たちに取材を重ねていたという背景があるからだ。普通のバブル本は、不動産価格の高騰とか、融資の総量規制とか、日銀の金融引き締めとか、マクロの指標から書かれていることが多い。しかし、本書は取材に基づいたミクロ面から描かれている。だから、バブル紳士たち、銀行、日銀、官僚、政治家といった人たちが、当時何を考え、どのように行動していたのかが、生き生きと伝わってくる。
新聞記者が書いたのだから、それは当然と思われるかもしれないが、当時の日経新聞に、これだけのリアリティーはなかった。本書のリアリティーは、バブルから30年の時が経過して、一種の時効が成立したために、当時は書けなかったことが書けるようになったこと、そして著者自身が歴史を俯瞰できるようになって、それぞれの事件を、歴史のなかに位置付けられるようになったからだろう。
著者の統一した歴史観に位置づけられたバブルの物語は、どれも興味深い。プラザ合意、山一証券の自主廃業、リクルート事件など、大きな出来事が、日本の経済社会の構造をどのように変えたのか、とてもよく分かる。バブルは護送船団方式の日本経済を市場原理主義に転換する役割を果たしたのだ。
そのなかで、バブル紳士たちの物語は特に興味深い。イ・アイ・イ・インターナショナルの高橋治則や秀和の小林茂などを、私はずっとマネーゲームを仕掛けた犯罪者だと理解してきた。しかし、本書で彼らの人となりや実績を知ると、単なる悪人と断ずべきではなく、歴史的にそれなりの役割を果たしていたことが分かる。また、日銀の三重野総裁も、私はバブル崩壊後の失われた20年を作ったA級戦犯と考えてきたが、本書には違った顔も描かれている。本書は、遺産として後世に引き継ぐべき出色の良書だ。★★★(選者/森永卓郎)