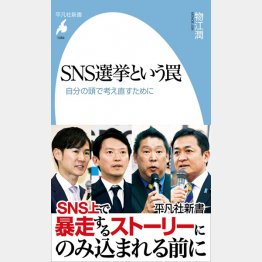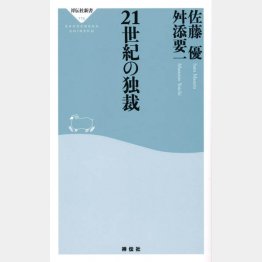選挙と独裁
『言った者勝ち』社会」朝日新聞取材班
合法的な民主選挙を経ているにもかかわらず独裁政権が生まれる。これが現代の異常事態だ。
◇ ◇ ◇
「『言った者勝ち』社会」朝日新聞取材班著
SNSとポピュリズムが組み合わさったのが現代。かつて中曽根康弘元首相は民意を「粘土と砂」に例えたという。粘土は労働組合や農協などの組織が人々をつないだ状態。しかし現在はそれらの組織の影響力が落ち、人々はバラバラの砂状になっている。すると砂を動かすにはショートフレーズを駆使したポピュリズムが効果的となるわけだ。さらに近年では都会でも田舎でもない「トカイナカ」にも変化がある。
例えば小田原は神奈川県の西部にあって人口密度も低いトカイナカだが、近年の投票行動では選挙のたびに選択を変える都会型の兆しがあるという。きっかけはコロナ禍。これで地域のつながりが弱まり、かつては午前と午後の2回行っていた夏祭りまで午前だけになるような変化があるという。
SNSの時代には世論調査も変わる。民意がころころ変わるため、従来の手法では予測がしづらくなった。2024年の東京都知事選での蓮舫候補の失墜などはその例にあたる。SNSの直接的な影響だけでなく、うつろいやすい現代の民意の社会背景を考える姿勢のめだつ好著だ。
(朝日新聞出版 957円)
「SNS選挙という罠」物江潤著
「SNS選挙という罠」物江潤著
SNSがいまや嘆かわしい流言飛語の温床になっていることは火を見るより明らか。利用者はどう対応すればいいか。ネットの片言に惑わされず自分の頭で考えようというのは正論だが、正論ほど通らないのが現代だ。
本書はそこにあえて正面から切り込む。著者は会社員から松下政経塾を経て文筆家になった今年40歳。特にNHKをぶっ壊すと叫んでSNSの流言飛語を徹底利用した立花孝志の政治手法を丹念に分析する。
続く章では学園闘争の盛んだった1960年代当時の大学生たちの政治熱と現代のSNSサイトでの盛り上がりの共通点を指摘する。当時の若者たちの心をとらえた吉本隆明の思想を考察するが、SNSの話とは一見無関係。熱狂する若者心理を操るSNSに対して「ストーリーを破壊する力」を吉本思想が与えるという点がキモだろう。
中年になっても「自分の頭で考え直す」(副題)ことが難しい現代への処方箋。
(平凡社 1100円)
「21世紀の独裁」佐藤優、舛添要一著
「21世紀の独裁」佐藤優、舛添要一著
どちらもクセ強の論客2人が対談で現代の「独裁」を論じる。一気にオンライン社会に移行した中国では高齢者でもスマホを使えないと生活ができない。キャッシュレス決済がすみずみまで張り巡らされて便利だが、これはカネの流れを当局がすべて把握すること。これで監視と独裁が実現する。
ロシアも同様。モスクワの生活水準は東京より高く、治安もよく、街にはゴミも広告看板もないという。これは「広告で人々の消費欲求を刺激する西側の経済と決別するということ」だ。しかも食品添加物を大幅に規制したためにパンも3日たてばカビが生える。市民はそれをむしろ歓迎する一方、ベンツやBMWなどは中東や中央アジア経由で新車が簡単に手に入る。ロシアへの経済制裁など物の数ではないというのだ。
対する日本の体たらく。SNSの流言飛語で政治家が跋扈するのは昔ながらの村落共同体が崩れたから。しかし全国的な政治勢力として展開するなら、地方の地元での地道な活動が欠かせない。そこが今後の注目点だという。
対談による本だが、往復書簡のような作りが特徴だ。
(祥伝社 1045円)