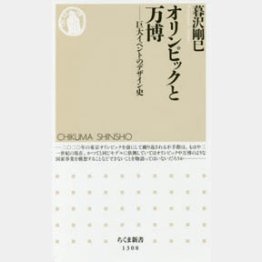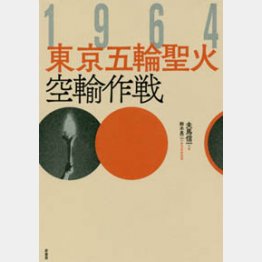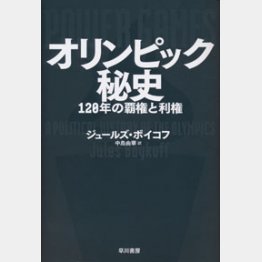オリンピック狂騒曲
「オリンピックと万博」暮沢剛巳著
史上最多の金メダルで鼻高々の平昌五輪チーム。「さあ次は東京だ」と関係者の鼻息は荒いが……。
1964年東京五輪と70年大阪万博を、「デザイン」の視点で振り返る――これが美術史を専門とする著者のコンセプト。
オリンピックと万博の共通点は、まず建築。代々木の国立屋内総合競技場の設計と、大阪万博の会場計画ならびに「お祭り広場」の大屋根の設計を担当したのは、共に丹下健三だった。著者は丹下の東大時代の指導教官だった岸田日出刀が、幻に終わった戦前の「紀元二六〇〇年記念」万博(1940年)の建築家だったことを明らかにし、政治的にはがらりと体制が変わったはずの戦前と戦後が、実は文化的につながっていたと指摘する。
戦前にはオリンピックも同じ年に計画されており、日本の軍国化でそれぞれ「返上」「延期」とされていた。そのため戦前の前売り券が戦後の万博で実際に使用されたという。ポスターのデザインも、あの日の丸模様で有名な東京五輪のシンボルマークをデザインした亀倉雄策が大阪万博の海外向けポスターを制作するなど、ここにも連続性が見られた。要するに戦前と戦後の五輪・万博はいわば反復だったわけだ。
終章では迷走する2020年五輪のエンブレムおよび競技場設計について詳しく論じている。 (筑摩書房 860円+税)
「東京五輪聖火 空輸作戦」夫馬信一著
前回、つまり1964年の東京五輪が「敗戦国ニッポン」の戦後復興を世界に披露するという「国威発揚」イベントであったことは、改めていうまでもない。
本書はこの“常識”を意外な角度から再検討する。
五輪につきものの聖火が、ギリシャのアテネから東京まで、どうやって運ばれたか、その元案から実際の空輸ルート、使用された飛行機の選定まで、当時の資料をふんだんに使って描き出す。著者は航空貨物の輸出業からコピーライターを経て編集者になったという変わり種。実は、当初の聖火運搬には、シルクロードを通る陸路の案もあったという。
しかし当時は鎖国状態にあった中国を通るのは不可能。他方、当時開発中の「初の国産旅客機」YS―11をぜひとも空輸に使いたいという関係者の悲願も強かった。航空専門家でもある著者は、マニアにも門外漢にも面白く読ませてくれる。
(原書房 2500円+税)
「オリンピック秘史」ジュールズ・ボイコフ著、中島由華訳
国家公務員ばりに五輪選手に身分保障を与える中ロとは対照的に、英米には文武両道を地で行くエリート出身のアマチュア選手が多い。本書の著者もそのひとり。
元バルセロナ五輪の米サッカー代表選手で、いまは政治学教授の著者が解き明かす“政治まみれのオリンピック史”が本書だ。
「五輪は政治に無縁」はIOCや選手団、NHKの中継アナまでが連呼するタテマエだが、むろんそれは表向き。近代五輪創始者のクーベルタン男爵からして「フランスを商業、軍事、植民地開発の分野におけるヨーロッパのリーダーにふたたび押し上げる」のが真の目的だったという。冷戦期には、米ソのボイコット合戦もあった。
日本向けの増補部分では原発事故の影響を「完全にコントロールされている」とした安倍首相の言葉を「そうとは思えない」と断言。今回の平昌の事前予想まで丁寧に触れている。
(早川書房 2200円+税)