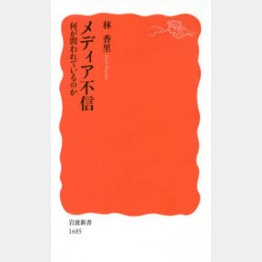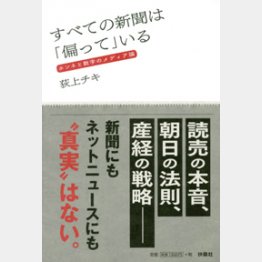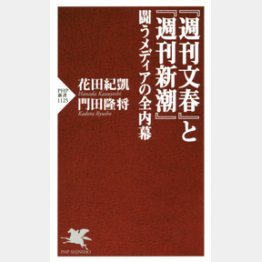国のトップが“フェイク”と切り捨て 危険なマスコミ不信に迫る
「メディア不信」林香里著
米大統領が気に入らない報道を「フェイクニュース」と呼び捨て、日本の首相がそれを真似る。大マスコミだけではない、危険なマスコミ不信に迫る。
◇
東大のメディア研究で大マスコミとは異なる「オルタナティブ・メディア」を専門とする著者。本書では独・英・米・日における昨今のメディア不信・批判を紹介しながら「民主主義とメディア」の関わりを論じている。
ドイツでは各州に新聞雑誌を規律する「州プレス法」があり、「公共的任務」を果たす義務がある。つまり、アメリカのように「言論の自由」が先行するのではなく、一定の制限がかかるのが当然とされる。ナチスの先例への反省から来るものだろう。
他方、日本は欧米のようにメディアへの市民の姿勢に国ごとの差異が明白に出るのではなく、メディアの内容を「他人事」「別世界」と受け止めているふしがあるという。「メディアへの問題意識」も薄弱だが、これは市民の側に政治参加の意識が薄いことの反映。しかもメディアの側がそれを利用して販促などを拡大してきた結果、「気がつけば人心が離れているのではないか」と著者は見る。要は“お上と下々”意識が庶民に強く、それを権力者ばかりでなく、大マスコミまでが利用してきたわけだ。ソーシャルメディアを論じた章では、一昨年の大統領選でトランプ陣営が綿密な「マイクロ・マーケティング」戦略を駆使したと紹介している。
著者は独英米のポピュリストのスローガンの大半が「日本の右翼の言葉」と同じだったことに衝撃を受けたという。まさに右傾化のグローバル現象なのだ。(岩波書店 840円+税)
「すべての新聞は『偏って』いる」 荻上チキ著
TBSラジオで、平日夜に毎日放送中の「荻上チキ・Session―22」。テレビのニュースバラエティーよりずっと硬派の内容でファンも多い。本書でも一見挑発的な書名ながら朝日新聞と産経新聞は何がどう違うのか、メディアによる「権力の監視」とは具体的に何なのかを最初に解説。
とかく放言になりがちなメディア批判ではなく、各新聞を丁寧に読み比べ、書評欄の中身まで見比べる。新聞を読む習慣自体のないミレニアム世代への配慮もあるだろうが、大上段の抽象論に流れないところがいい。(扶桑社 1300円+税)
「『週刊文春』と『週刊新潮』」 花田紀凱、門田隆将著
過激なスキャンダル報道週刊誌といえばこの2誌。それぞれの元編集長が心おきなく語った、というのが本書。「文春」は人事異動が多く、編集長も2年程度で交代。逆に「新潮」は固定の勤続スタッフが大半で、取材するデータマンと文を書くデスクは完全分業。「文春」は担当者が取材から執筆までオールラウンドでこなすという。
昔は両誌ともスクープをテレビにパクられてばかりだったが、最近では記事の使用料が払われ、動画があると料金もグンとアップ。「このハゲーっ」では「新潮」編集部に1500万円の実入りがあったとか。「文藝春秋」の名編集長・池島信平が“スキャンダルを書かれた当人が苦笑する程度にとどめろ”と言ったという故事、「文春砲」のいまでは考えられない昔話だ。(PHP研究所 880円+税)