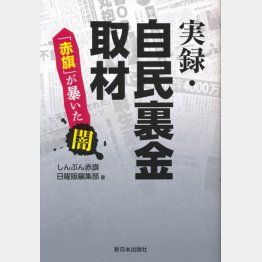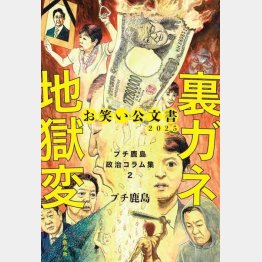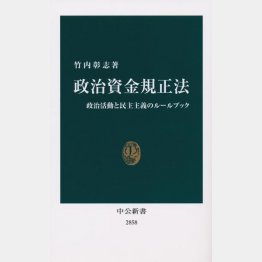裏金政治のていたらく
「実録・自民裏金取材」しんぶん赤旗日曜版編集部著
今月20日に迫る参院選。早くも自民大敗が噂されるのは、裏金政治のおかげだ。
◇
「実録・自民裏金取材」しんぶん赤旗日曜版編集部著
今回の裏金問題を暴いたのは日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」。失礼ながら大手マスコミとはいいがたい。同紙編集部がまとめた本書でも、英「エコノミスト」紙が今回のスクープを「共産党の比較的無名の新聞」と紹介したことを面白そうに伝えている。
新聞メディアならではの地道な調査報道はどのようになされたのか。本書はそれを明らかにする。
発端はコロナ騒動さなかの2021年12月。国交省官僚出身の自民党参院議員の政治資金パーティーを同紙の記者2人が取材したこと。感染防止のため立食パーティーすらなく、ゼネコン業界の大物がずらりと壇上に並ぶセミナー形式の「パーティー」には水1杯出ないのに会費は2万円。この不自然さに疑問を抱いたことが取材のきっかけとなった。コロナ禍で世間が苦しむ中、政治資金パーティーだけが規制をくぐりぬけて荒稼ぎのボロもうけをしていることに気づいた同紙は、さらに自民党では企業からの献金を議員ごとに割り振って足し合わさないことで企業名が表に出ないようにしていることを突き止めた。
取材の過程はまさに迫真のドキュメント。最初に取材した2人の記者はどちらも安倍元首相の「桜を見る会」疑惑を取材したベテランだという。 (新日本出版社 1540円)
「お笑い公文書2025裏ガネ地獄変 プチ鹿島政治コラム集2」プチ鹿島著
「お笑い公文書2025裏ガネ地獄変 プチ鹿島政治コラム集2」プチ鹿島著
漫才師が首相や政治家の形態模写などで笑いを取っていたのはとっくの昔の話。近ごろはお笑いが政治を取り上げると正々堂々の政権批判になる。その筆頭が著者だろう。いまや時事ネタ芸人としての定評を確立した感があるが、その本領を発揮するのが本書。「文春オンライン」の各新聞の読み比べ連載コラムから生まれた第2弾だ。
たとえば昨年10月末の記事。自民の反主流派で“党内野党”だった時代は「なんか自民党、感じが悪いよね」の発言がバズったこともある首相だが、「その石破氏が遂に首相となり、何が変わるのかと見ていたら本人が豹変した」とバッサリ。裏金問題をすっぱ抜いたしんぶん赤旗の報道に対して「私どもはそのような報道に負けるわけにはいかない」と、安倍元首相が街頭演説で言い放ってヒンシュクを買ったのとそっくりな発言と指摘。「悪夢のような民主党政権」という安倍氏が好んで用いたフレーズも使い出したという。「なんか安倍氏に似てきた」と、コトバはさりげないが、これぞ当世の政治風刺。
昨年のクリスマスイブも、直前に死去した渡辺恒雄読売新聞主筆が病室で論説委員長が持参した元日の社説を細かくチェックしたという記事を伝える。まさに眼光紙背に徹しての新聞読みコラムだ。 (文藝春秋 1760円)
「政治資金規正法」竹内彰志著
「政治資金規正法」竹内彰志著
「政治資金規正法違反」が裏金問題の正式な名前。この法律ができたのは敗戦後の占領下。アメリカの腐敗行為防止法を手本に政治団体の収支を限定的に公開するための法律だった。政治家個人ではなく政治団体が対象だ。公開と引き換えに繰越金は非課税の対象となる。そこで政治団体を通じた資金の出入りが増え、不祥事も起こりやすくなるわけだ。
ちなみに国会議員は本人と公設秘書の給与が税金から支払われるが、地方議員には公設秘書の制度自体が存在しない。そういう初歩から現役弁護士の著者が丁寧に解説するのが新書のいいところ。
法律ができた当初は政治資金パーティーもやりたい放題だったが、1982年の改正でパーティーは政治団体が行うべきとされた。これは法律上必須の規定ではなく、訓示的な規定とされる。要は努力目標ということで、憲法で定める集会の自由とのバランスをとったためだ。
複雑な仕組みを持つ政治資金規正法だけに論点も多様。選挙民が知っておきたい基礎知識集だ。 (中央公論新社 1034円)