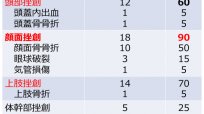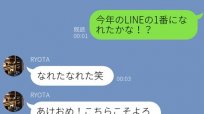日本経済を襲う「2024年問題」の深刻度…迫る“物流クライシス”に業界も消費者も戦々恐々

「物流は経済の血液」といわれるように物流は経済のインフラだ。しかし、荷物があるのに送れない状況も生まれつつあり、さらには迫りくる2024年問題への対応に現場は必死だ。他人事ではなく、私たちの暮らしにも大きく関わってくる問題だ。
◇ ◇ ◇
「関東で自宅療養者に…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,365文字/全文2,506文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。