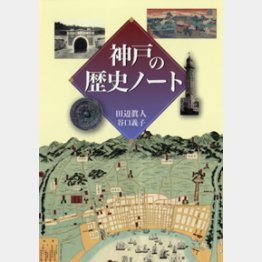「神戸の歴史ノート」田辺眞人、谷口義子著
大都市としてのミナト神戸を捉えるときに、「兵庫」という2文字の意味が大きく変わる。
すなわち神戸は、古代からの難波津つまり大坂の外港として「兵庫津」のあった都市であり、その意味では大坂同様の摂津国内の都市だ。
一方、「兵庫県」としてみる場合は、神戸は摂津・播磨・淡路・但馬・丹波と日本海側から瀬戸内海側に至る風土も方言も違う5国による大県の県庁所在地である。だから神戸近辺で「ご出身は」とか「お住まいは」と聞いた答えが「兵庫」ですと返ってきた場合、神戸市の兵庫区を意味する。姫路にしろ但馬にしろ、彼らは兵庫(=県)生まれという言い方はしない。
さてその神戸、六甲山系と大阪湾に挟まれた風光明媚な神戸は、畿内・摂津の西端に位置していて、在原業平が古今和歌集に詠み、紫式部は源氏物語で光源氏の隠棲場所とした。
平清盛が平安京を移した福原と日宋貿易の大輪田泊。義経の「鵯越の逆落とし」で有名な源平合戦の一ノ谷。南朝の楠木正成が足利尊氏に敗れて自害した湊川は、いずれも現在の神戸の中心街の近くにある。
“兵庫県の中の神戸”という見方をしていると、神戸はもともと摂津の中の一つのエリアだったという重要なポイントを見落としてしまう。これは神戸の歴史を知ることで痛感することだ。
18世紀末の天明期以来の「江戸積み」を行う「摂泉十二郷酒造仲間」は、大坂三郷・伝法・北在・池田・伊丹・尼崎・西宮・兵庫・堺・今津・上灘・下灘である。堺以外すべて摂津である。その後、幕末明治になって神戸市東部の上灘が西宮、今津を加えていわゆる「灘五郷」として発展、日本酒の大名産地名として称されることとなった。
この本は兵庫県史編纂委員の田辺眞人さんが神戸市職員新規採用者を対象に行った、神戸の通史講義の際のノートがもとになっている。時代区分によって5章に分かれた章末の自修ノートもやってみて面白い。
(神戸新聞総合出版センター1300円+税)