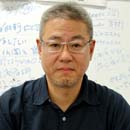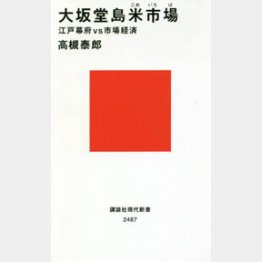「大坂堂島米市場」高槻泰郎著
商品先物取引などやったこともないし、なんやようわからん、勝ち逃げ称賛のばりばりの金融資本主義と違うのだろうか。
そう思うのだが、「売りたい時に売れない、あるいは買いたい時に買えない状態を、当時の人は『手狭』と表現している。『手狭』は大坂商人が嫌った言葉で、その対義語が『手広』である」。
「手狭」「手広」という大阪弁をつかってそう説明される。「手広」く商いをしたいから、現金と米切手をやりとりするのではなく、「売りと買いの約束」を取り交わすことの取引があればよいのではないか。この発想が「帳合米商い」の原点である。今の言葉なら「流動性の高い市場」なのか。一気に分かるような気がするのは自分が大阪弁話者だからだろうか。
その現場、堂島、中之島あたりを、
「上部を流れる大河が大川(淀川)で、中之島と呼ばれる中洲によって堂島川(北)と土佐堀川(南)に分かれる。中之島北部にかかる大江橋と渡辺橋の間に『米市場』と書いてある場所こそ堂島米市場であり、現在は記念碑が建っている」
と、「江戸時代のウォール街」といった見出しで書かれ、見開き地図付きで解説しているが、何を隠そう今キーボードを叩いているわたしのオフィスは大江橋北詰にある。だからとてもリアルに伝わってくる。
いまも商社や銀行が立ち並ぶ関西屈指のビジネス街。本に挿入されている「浪花名所図会」などの様子はすっかり様変わりしているが、売買に際して買いを「取ろう取ろう」、売りを「やったやった」と声が飛び交ったとされる大阪弁は続いているのだ。
人口成長が停滞していた江戸中期以降、米がとれすぎると輸出もできず、直ちに米価下落につながる鎖国構造で、幕府が米価を安定的に上昇ないし維持しようとする「買米令」の顛末など、マーケットと政府の押し合いへし合いが大坂・堂島を舞台に繰り広げられたさまざまな記録。これが圧巻だ。
(講談社 900円+税)