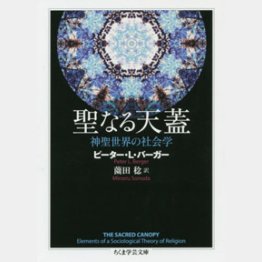社会の秩序への疑念に目覚めた子どもたち
キリスト教系の小学校に通う子どもたちは、小3ごろまで「イエス様」を素直に信じている。だが、もう少し経つと怪しくなり、やがて「イエス様っていないんだよ」と言い出す。それは社会の秩序というものが「あてがわれて」いることへの疑念に目覚めるからだ。――そんな幼くも真剣な姿を、巧みな距離感と小さなユーモアを交えて描いたのが先週末から公開中の映画「僕はイエス様が嫌い」である。
前評判は奥山大史監督が弱冠22歳の新鋭だとか、スペインのサン・セバスチャン国際映画祭の最優秀新人監督賞を受賞したといった話ばかり。しかし本作の面白さは、小面憎いほど世慣れた当節風の器用さと、時代が変わっても繰り返される秩序への疑念とが上手にミックスされ、なお若手らしい清潔感をたたえているところにある。絵作り、演出、物語。そのバランスの良さを賞玩しながら、終幕部で発せられる問いかけを真顔で受け止めたいと、そう思わせられるのである。
「神の不在」を多くの人間が口にする現代は、神を素直に信じていた前近代とはまったく様相が異なる。そんな社会の生きづらさや秩序の難しさを根源的に考える学問のひとつが社会学だ。
ピーター・L・バーガーの「聖なる天蓋」(筑摩書房 1200円+税)はアメリカの著名な社会学者による信仰と社会秩序の関わりについての古典的著作。バーガーは人間の意識が社会構造と触れ合うことで社会という「現実」がつくり出されるのだとする「現象学的社会学」の泰斗。その一方、神学者として、宗教が無条件に効力を発揮できない近現代の「世俗化」をどう捉えるべきかについて「聖なる天蓋」の後半で議論した。聖なるものが消失した「根なし草」の時代。バブル以後の沈滞した日本社会はなおさらなのではないか……。 <生井英考>