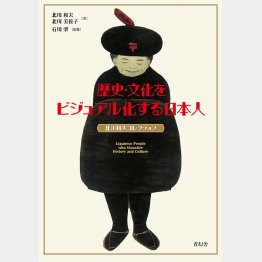「歴史・文化をビジュアル化する日本人」北川和夫、北川美佐子著 石川肇監修
「歴史・文化をビジュアル化する日本人」北川和夫、北川美佐子著 石川肇監修
大衆文化研究を専門とする本書の監修者・石川氏(京都日本文化資源研究所所長)によると、「日本人は歴史や文化をビジュアル化するのが得意で、好きな民族」だそうだ。
確かに、「鳥獣人物戯画」や「源氏物語絵巻」「百鬼夜行絵巻」などの古典から、世界中でヒットする現代のアニメまで、そのDNAが生み出したものを見れば一目瞭然だ。
本書は、そんな日本人が作り出し、楽しんできたさまざまなアイテムを収蔵する京都の「想い出博物館」(現在は休館中)のコレクションを紹介しながら、日本人や日本文化について考察したビジュアルブック。
太陽神・天照大御神が天乃岩戸から誘い出される日本神話のあの場面も、目にした者はいないはずだが、さまざまにビジュアル化されてきた。
マンガでも使われる集中線を効果的に使った三代豊国の浮世絵版画や、八咫鏡(やたのかがみ)などを背景に神々を配置して表現した飾り人形などを取り上げる。
日本神話の絵画化が活発になるのは近世・近代からで、大正時代のはがきには初代天皇とされる神武天皇が描かれる。その手に持つ弓の上には建国に助力した「金鵄(きんし)」が止まっている。
江戸幕府の切支丹禁止令によって始まった「絵踏」だが、正月に行われる丸山遊女の絵踏は、人気遊女の生足が拝めると群衆が押し寄せる人気行事でもあったという。
それを表現した長崎風俗人形や、ちょんまげの男性がコンデンスミルクを飲む姿を描いた大正2年ごろの広告、「フキダシ」を日本で最初に使った漫画「正チャンの冒険」と正チャン人形型の自動菓子販売機(大正13年ごろ)など。
江戸後期から昭和まで浮世絵やポスター、おもちゃ、人形など約300点もの図版で、あらゆる事象をビジュアル化してきた日本人の足跡をたどる。
(青幻舎 2970円)