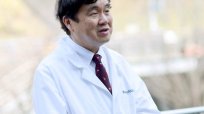死を身近に感じたことで…訪問診療医が実感した「新型コロナ」の教訓<下>
「発熱時に対する不安を口にする人が増えました。それで私は、PCR検査の基準や指定医療機関のことに始まり、救急車を要請しても迅速な受診が見込み薄であること、陽性ならば面会が制限されること、陰性で全身状態が安定していれば自宅療養の可能性が高いことなどを説明するようになったのです」
その結果、治療計画を変更する人もいた。老老介護する妻の負担を考え、緩和ケア病棟への入院を検討していた末期がんの男性患者(89)のケースである。
「夫はほぼ寝たきりで、妻は認知力が低下していました。妻主導の介護は厳しい状況でコロナの流行前から入院を考えていたのですが、予定していた病棟はコロナ対応で面会制限を設けました。そのため、入院が今生の別れとなる可能性が生まれたのです」
そこで入院を回避し、ケアマネジャーによる手厚い介護のもと、自宅療養をすることになった。患者は5月下旬に亡くなったが、その前日には娘が遊びに来て、当日は入浴サービスを受け、リンゴのすりおろしも数さじ味わったという。穏やかな最期だった。
「現在は未知のものに対する恐怖から過度な対応が目立つように思いますが、もともと死はごく身近に存在するものであり、そのことを意識する者だけが自らの死に思いを致すことができるのです」
死はいずれ誰にでも訪れるものだ。事故などで予期せず逝ってしまうこともあるが、多くの場合、どのように迎えるかを自分で選択できる。コロナの流行を無駄にはしたくない。
(おわり)