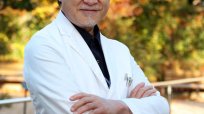(43)小さく手を振り見送る母の姿に、涙が止まらなくなった
母が施設に入った頃、不思議と夢をよく見た。普段は目覚めると忘れてしまうのに、いくつも覚えているものがある。
ひとつは、母が父の遺品でごちゃごちゃになった部屋をてきぱきと整理してくれる夢だった。思わず「あれ、お母さん元気じゃん」と思ったが、夢だった。そんなことは起きないとわかっているのだけれど、起きたらいいのにと願った。
また別の日には、父が真新しい青いパジャマ姿で夏布団を持ってきてくれる夢を見た。「ありがとう」と受け取ってから、「あれ、でも数カ月前に死んだはずでは」と思い、「今日って何月何日だっけ?」と尋ねた。父は少し悲しそうにほほ笑み、ふっと姿を消した。
夢から目覚めて現実に戻ると、さまざまな書類の「緊急連絡先」という欄で手が止まる。父は亡くなり、電話の受け方すらわからなくなった母は施設に入った。きょうだいもパートナーも子どももいない。私に万一のことがあったとき、いったい誰に連絡を受けてもらえばよいのだろう。
一軒家の実家では、朝夕に虫の鳴き声がどこからともなく聞こえてきて、月光も日差しも雨も惜しみなく降り注いでくる。その自然との距離の近さが、東京の暮らしではすっかり感じなくなっていた「生」の感覚をまざまざと呼び戻す。