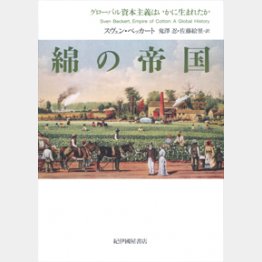「綿の帝国 グローバル資本主義はいかに生まれたか」スヴェン・ベッカート著、鬼澤忍、佐藤絵里訳
「綿の帝国 グローバル資本主義はいかに生まれたか」スヴェン・ベッカート著、鬼澤忍、佐藤絵里訳
柳田國男は「木綿以前の事」のなかで、室町時代後期に日本国内で木綿が広く普及した原因として、それまでの麻に比べて肌ざわりの良さと染色のしやすさを挙げている。本書の著者も、やわらかく、耐久性があり、軽い上に、染めやすく、洗いやすいという特性が、綿をほかに類のないグローバルな商品に押し上げたのだと指摘している。
5000年ほど前、インド亜大陸で綿の繊維から糸をつくれることが発見されて以来、綿製品が南北アメリカ大陸、アフリカ大陸、アジアと広まっていくが、15世紀末からの大航海時代を機に、ヨーロッパを中心にした「綿の帝国」ともいうべき広大な商業ネットワークが形成されることになる。本書はこの「綿の帝国」の興亡をたどった物語だ。これは同時にグローバル資本主義の構築と再構築の物語でもある。
帝国の推進力となったのは奴隷制を中核とする暴力的なシステムであり、著者はこれを「戦争資本主義」と名付けている。ヨーロッパの帝国主義国家による広大な植民地の収奪、先住民の大量虐殺と資源の強奪、人間の奴隷化等々。
これらによってそれまでの経済空間の構造は大きく変化したが、その中心にあったのが綿だった。綿の栽培から製品化という過程において、必須とされたのは安価な労働力だ。米国南部の黒人奴隷、イギリスの児童と女性労働者、戦前日本の「女工」などの安価で隷属的な労働力なしには「綿の帝国」が築かれることは決してなかったと、著者は強調する。
その後、戦争資本主義は後退し、契約と市場を重視する産業資本主義に取って代わられ、労働者も自らの権利を獲得するに至るが、現在のグローバリズムにおいても、弱者への暴力的なシステムが底辺を支えているという構造はいまだに引き継がれている。700ページにも及ぶこの大著は、今後の資本主義の行方を見定めるにおいて重要な示唆に満ちている。
<狸>
(紀伊國屋書店 4950円)