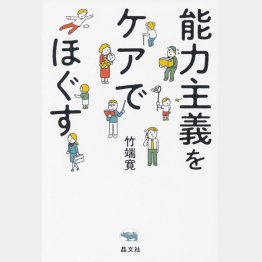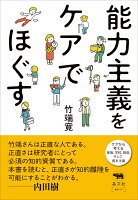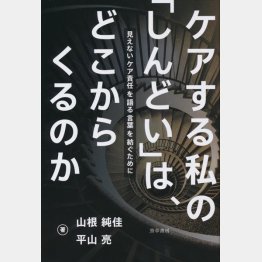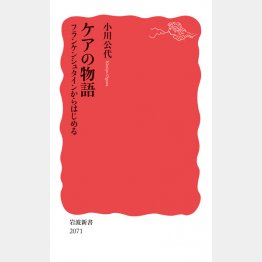ケアと癒やし
「能力主義をケアでほぐす」竹端寛著
子育ても介護も、傷ついた友や自分への癒やしも、すべては「ケア」という時代。
◇
「能力主義をケアでほぐす」竹端寛著
先ごろ、某大手商社が部長級で最大3000万円超、課長で2000万円超という高額給与を発表して話題になった。もちろんこれは能力給制度ゆえ。これがメリトクラシー(能力主義)だ。IT企業などはかねて能力主義を公然と主張してきたが、近ごろでは商社や銀行ばかりか製造業にまでじわじわと広まっているようだ。
本書は福祉問題を専門とする社会学者のエッセー集。もとは個人のブログで書いたものを再編集したというだけに主観的・情緒的な書き方で身近な問題に迫る。
たとえば大学を偏差値で分けて最底辺を「Fランク」と小バカにする風潮は、逆に上位校の学生たちが自分をランク付けする習慣に染まっているからだと指摘する。「それは、かつて受験勉強を必死にするうちに偏差値を内面化してきた自分自身と重なるのだ」
子育ての話も、子どもが生まれてからは仕事での外出や出張を減らしたら睡眠時間が確保できた。また妻は別室で子どもと寝ているが、「あなたが一緒に寝ていても特に役立たないし、必要なら起こしに行く。それよりは、夜は寝て、日中ガッツリ家事育児して仕事もしてくれた方が助かる」からだという。身近なところから社会を語る独白調の論集。 (晶文社 1870円)
「ケアする私の『しんどい』は、どこからくるのか」山根純佳、平山亮著
「ケアする私の『しんどい』は、どこからくるのか」山根純佳、平山亮著
子育てもケア、高齢者介護もケア、しかもその多くは女性にかぶさってくるのもまた事実。しかし本書はそれを単純に女性差別と決めつけるわけではない。
たとえば3.11東日本大震災の原発事故で、遠方に引っ越すなどした母親たちの行動は「感情的」「非科学的」「自己中」と非難された。しかしケアする人間の視点から見れば子どもの健康により良い行動をとるのは非合理ではないはず。むしろ男たちの「理性的」な行動は子どもをケアする立場にないからともいえるはず。
こうした論理で本書はケアを押しつけられがちな女性の立場を論じ、さらに家族ならケアして当然とする習慣や風潮に切り込んでゆく。合計6人の筆者はすべて日本全国の大学で教壇に立つ社会学者。彼らの視点には世代の影響もあるのではと思われるが、巻末の略歴に生年の記載がないのは惜しい。学者にも世代差はあって当然。それを考える一助があるとよかった。 (勁草書房 2530円)
「ケアの物語」小川公代著
「ケアの物語」小川公代著
メアリー・シェリーの小説「フランケンシュタイン」は今からおよそ200年前に発表された書簡体小説。本書はシェリーの伝記を翻訳した著者が、「フランケンシュタイン」に触発されながら近現代のさまざまな物語を読んでゆくエッセー集。
きっかけは難病を患った実母のケア。その際、学者になるべく海外留学などに挑む著者を常に支えてくれた母のようなケアラーのことを「心のどこかで軽んじていた自分」に気づかされたのだという。そこから、生まれてまもなくの子どもを亡くしたという心の傷を負ったシェリーによる怪物の物語を読み解きながら、「吸血鬼ドラキュラ」「親ガチャの哲学」「鬼滅の刃」「虎に翼」「ダロウェイ夫人」などを次々に論じてゆく。
これまで男性筆者中心だった論壇誌を初めて女性編集長がリニューアルした岩波書店の雑誌「世界」に連載されたものだけに意欲的な筆致があふれる。
原作の小説やドラマや映画を見ていないとわかりづらい点が目立つのが惜しい。 (岩波書店 1100円)