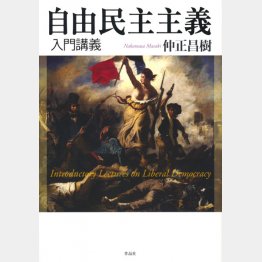「自由民主主義入門」仲正昌樹著/作品社(選者:佐藤優)
異論を許さない社会…いまこそ愚行権の重要性を強調する意義
「自由民主主義入門講義」仲正昌樹著/作品社/2025年
日本は自由と民主主義を基本とする社会のはずだ。しかし、ネット空間を中心に異論を許さない傾向がある。そして、ネット空間での議論の濃度がある臨界を超えると、それが新聞やテレビにも及ぶ。コロナ対策の行動規制、ロシア・ウクライナ戦争、旧統一教会問題などで、異論を許さない傾向が顕著になった。こういう傾向が社会を弱体化させる。社会が弱くなると、当然国家も弱くなる。国際社会において国家エゴが強まり、帝国主義の時代が再来しているような状況で日本国家が弱くなると、国民が不幸になる。
自由をめぐる問題を近代自由民主主義の原点に立ち返って仲正昌樹氏(金沢大学教授)が考察する。ミルの自由論の解説で、仲正氏は愚行権の重要性を強調する。
<「第二に、この原理(引用者注*自由の原理)は、何を好み何を目的にして生きるのかという点での自由を要求する。つまり、自分自身の性格に合った生活の仕方を作り上げていく自由であり、生じてくる結果を引き受けつつ、自分のしたいことをする自由である。本人のすることを他の人々が愚行であるとか、常軌を逸しているとか、不適切だとか考えたとしても、彼らに危害がおよんでいるのでない限り彼らから妨害されない、ということである。」/これが幸福追求権、特に憲法学で愚行権と呼ばれているものですね。「愚行」の原語は〈foolish〉です。どんなにバカに見える行為でも本人が自分の幸福だと思ってやっていることに干渉することはできない>
例えば、野良猫を保護して一生飼うと、猫の寿命は15年程度なので、餌代、トイレの砂代、病院代などで200万円程度かかる。評者は2005年に職業作家に転じてから8匹の猫を保護した。そのうち、5匹は天国に旅立った。猫嫌いからすれば、そんなカネは無駄だからもっと社会的に意義のあることに使えということになるのだろうが、それを評者に強制することはできない。猫を保護し、飼うことが評者の愚行権だからだ。
猫を放し飼いにすれば他者に危害や迷惑をかける可能性があるが、屋内飼いならばそういう事態も生じない。この愚行権を言い換えると、各人の幸福追求権になる。幸福は国家や社会ではなく、個人が決めるものなのである。
インターネット空間では愚行権を認めない傾向が強い。自分にとって絶対に正しいことであっても、他の人にとってそうでない場合がいくらでもある。人間は神のような全知全能の存在ではないので、なにがほんとうに絶対に正しいことであるかを確定できない。「絶対に正しいことは存在する。ただしそれは複数ある」という多元性と寛容の精神を本書から学ぶことには現代的意義が大いにある。 ★★★
(2025年11月13日脱稿)