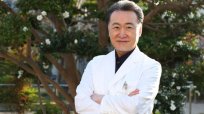(1)相次ぐ氷河崩壊…未知のウイルスによる感染爆発の可能性
この溶解は北極圏に限らない。アンデスでは過去60年間で熱帯氷河の6割が消滅。日本ではかつては富士山(標高3776メートル)、北アルプスの立山(3015メートル)、北海道の大雪山(2291メートル)で永久凍土が広がっていた。しかし、富士山では1935年に3100メートル以上で見られた永久凍土が、2007年には部分的な永久凍土でさえ3500メートル以上でないと見られなくなっている。この現象で懸念されるのは、雪氷で閉じ込められていた未知のウイルスとの遭遇だ。現に2016年の夏にはシベリアの12歳の少年が炭疽症で死亡した。致死性の強い炭疽菌の胞子を体内に宿したまま凍土に埋もれたトナカイの死骸が熱波により地表に現れたことが原因だった。このとき約90人が炭疽症を発症し、約2000頭のトナカイが死亡した。
アラスカではスペイン風邪の犠牲者が永久凍土内に埋葬されており、ウイルス再出現の懸念もある。長崎大学感染症研究出島特区ワクチン研究開発拠点拠点長の森田公一同大教授が言う。
「近年フランスの研究チームが永久凍土の中から古代の巨大ウイルスを採取し、それらが感染力を維持していたと話題になりました。しかし、永久凍土の自然溶解による突発的な感染爆発の可能性よりも、私が現実的な懸念と考えているのは、動植物の北上や開発に伴う『スピルオーバー』による新たな感染爆発です」 =つづく