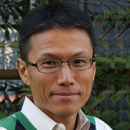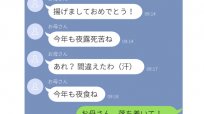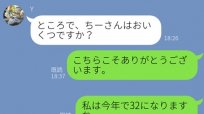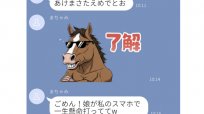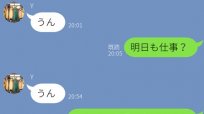明治政府が閉じた琉球王国450年の幕 日清戦争で日本領に

2019年10月31日未明、衝撃的な映像が世界に流れました。琉球王国時代の王府首里城が焼失したのです。沖縄の皆さんへのエールをこめて、今回は琉球王国の歴史をたどってみましょう。
■中国の方が近い
地図(1)は那覇を中心として同心円を描いたものです。一見してお分かり…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,759文字/全文2,900文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。