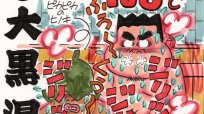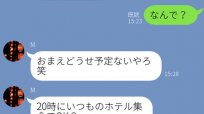要介護一歩手前「フレイル」改善を実証したシニア向けマンションの取り組み

各地の公園などでは花見が行われ、行楽を楽しむ人の姿が目立つ。ゴールデンウイークの観光地は、さらに人出が増えるだろう。アフターコロナを歩み始めたいが、「やりたいことが分からない」という人もいて、そこにフレイルが関係しているという。
◇ ◇ ◇
「年齢を重ねると、…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り2,902文字/全文3,043文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。