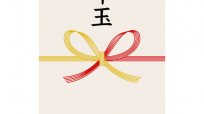男子メークの源流は飛鳥時代にあり? イケメン評論家が語る「美意識の歴史」
時代とともに“イケメン像”は変化してきた。発売中の『究極の推し活手帳・イケメン学習帳』(日興企画)著者で、イケメン評論家・沖直実さんは、数々の文献から男の美意識の歴史を分析したという。飛鳥時代、平安時代、そして現代まで、イケメンの歴史を振り返る。
◇ ◇ ◇
「当時、中国は唐の時代。文化交流も積極的でした。遣唐使は全員眉目秀麗な男子(イケメン)で構成されていたなんて説もあります。やっぱり日本の代表として海外に行くわけですから、見た目も重要だったのかもしれませんね」
この時代には、美しすぎて命を落としたイケメンがいたという。
「天武天皇の第3皇子、大津皇子は、あまりに美しすぎたせいで嫉妬され、謀反の疑いをかけられて処刑されたと言われています。よほど外見のインパクトがあったんでしょう」
平安時代になると、男性の美意識は高まっていった。お歯黒をしたり、白粉を塗ったりして、中性的な美しさが理想とされるようになった時代だ。
「その後、室町時代になると能やお祭りの舞台で白塗りの化粧が登場します。安土桃山時代になると衣装も派手になり、江戸時代は歌舞伎文化が始まって“隈取”が出てきます。その頃、遊郭で働く男性は色気づいて眉を描く人もいたようです」
それでも、庶民が化粧するという文化はまだまだ縁遠かった。