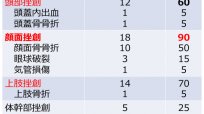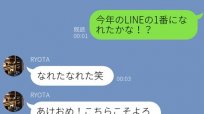戦後80年。無関心な若者たち…「戦争を語り継ぐ」ことを困難にしているのは誰か
私は日本が戦争に敗れた年の秋に生まれた。激動の「戦後80年」は私の人生とそのまま重なる。
戦争は知らないが、戦争が残した“傷痕”は知っている。疎開先の新潟から東京に戻った時、駅のホームから見た一面の焼け野原。傷痍軍人がいた。そこここにバラックといわれた掘っ立て小屋が立ち並び、ラジオの「尋ね人」は「シベリアに抑留されていた○○さん、一報ください」と呼び掛けていた。
皆一様に貧しかった。だが、今日より明日はよくなると信じられた時代だった。
それから80年が経ち、今年も「8月ジャーナリズム」とヤユされる戦争回顧の季節が来た。新聞には「被爆80年 もう一度原点に」などの文字が躍る。だが、私は忘れない。2011年8月15日を「新聞休刊日」にしたことを。だいぶ前から、報道の現場には使命感も危機感も“消失”しているのだ。
メディアはよく、田中角栄の「戦争を知らないやつが出てきて日本の中核になったときが怖い」、歴代幹事長、野中広務の「日本人はすぐ一色に染まるから怖い」、梶山静六の「政治がやらなければいけないのは、有事の法整備をしても、それを行使しないための外交なんだ」、古賀誠の「外交以外に平和を保てない。9条堅持。理想論だというなら何が悪い。理想を実現するのが政治だ」という言葉を引用する。