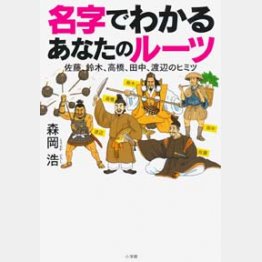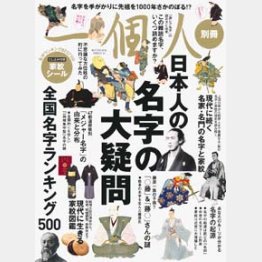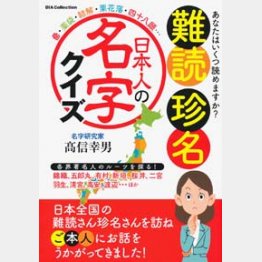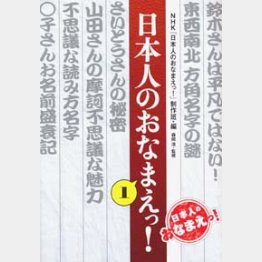名字探究本特集
自分の下の名前の由来を説明できる人は多いが、では名字はどうだろう。そのルーツをどれだけ知っているだろうか。名字とは、自分がどこからやってきたのかをたどることができる最高の履歴書だ。今回ご紹介するのは、名字探究に役立つ4冊。日本の歴史や文化的背景までもが見えてくる、ロマンにあふれた名字の世界へようこそ!
「江戸時代は武士以外には名字がなかった」。一定の年代以上の人は、小学校でそう習ったはずだ。ところがこれ、今では明確な誤りとされている。森岡浩著「名字でわかるあなたのルーツ」(小学館 1200円+税)では、名字研究の第一人者である著者が、名字自体のルーツから各名字の由来、分布について解き明かしている。
一般庶民が名字を持つようになったのは室町時代であるという。6世紀ごろから蘇我馬子や物部守屋などの人名を名乗っていた豪族はいたが、蘇我や物部は名字ではなく「氏」。先祖を等しくすると考える、血縁集団の名称だ。また、藤原や平などは「姓」であり、国から与えられた公的なもの。一方、名字は自らの意思で名乗ることのできた私的なものだ。
その名字が使われ始めたのは、氏族の衰退が進み、有力な一族の姓が増えすぎて区別がややこしくなってきた平安時代。そして、貴族や武士に広まった名字が一般庶民にまではやり出したのが、室町時代と考えられている。
名字は自由に変えることもできたし、兄弟で違うことも珍しくなかった。そのため、名字は増えに増えた。現在、日本にいくつの名字が存在しているかは、何と政府も把握していないのだという。著者の推測によれば、漢字の読み方や組み合わせを考えれば、20万種類近くになるそうだ。
実に多彩な日本人の名字だが、その由来もバラエティーに富んでいる。例えば、平安時代になると有力な貴族や寺院が私的に所有・経営する土地である荘園が増加した。この荘園の管理をする仕事が荘司であり、「しょうじ」さんのルーツとなった。今では書き方は「荘司」「庄司」「東海林」とさまざまあるが、いずれのルーツも荘園の管理者と考えることができるという。室町時代になると商業が盛んになり、増えたのが金融業者の「土倉」。現在の「とくら」さんや「はくら」さんのルーツだ。
名字の読み方によって出身地域が分かるケースもある。東と書いて「ひがし」さんと呼ぶ場合、それは単に村の東側に住んでいたなどの由来である場合が多く、出身地域は定かでない。問題は、「あずま」さんだ。平安時代以降、都の人々は京都から東側を「あずま」と呼んだ。そのため、東と書いてあずまと読ませる名字は、ほとんどが近畿以東に分布している。たとえ先祖代々九州に住んでいると思っていても、名字が「あずま」さんならそのルーツは関東や東北の場合があるということだ。
知れば知るほど面白く奥深い日本の名字。本書では2500超の名字について言及しているため、あなたのルーツも見つかるかもしれない。
「一個人別冊 日本人の名字の大疑問」
名字の起源やメジャー名字の由来、名字の分布図など名字にまつわるあらゆるデータとともに、名字とあわせて日本人が家単位で伝えてきた家紋についても、ひもといていく。
家紋の起こりは平安時代中期で、貴族の藤原実季が自身の牛車を見分けるために、巴形を三つ組み合わせた独自の意匠をつけたことに由来するといわれている。そして、家紋を見ると名字の起源も分かってくる。
藤原姓を起源とし、一族から台頭して伊勢神宮で役職に就いた佐藤一族の家紋は、朝廷からの貢物を運ぶ牛車をモチーフにした「源氏車」が多い。ほかにも、藤原一族であったことを象徴する、藤の花をあしらった「下がり藤」の家紋も多いという。
名字の多様性とともに、日本の家紋のデザイン性にも感心させられる。
(KKベストセラーズ 824円+税)
「難読珍名 日本人の名字クイズ」高信幸男著
「九」と書いて、何と読むだろうか。「きゅう」に決まっているが、名字となると違ってくる。
答えは「いちじく」で、全国にたった1軒だけあるという。その由来は「一文字の九」だから、あるいは祖先が医師をしており、治療まで「一時苦しい」からとも伝えられているそうだ。
本書では、「薬袋」「先生」「一寸木」など、全国に実在する珍名とその軒数や由来についてクイズ形式で紹介している。
ほかにも、各界著名人の中からの変わった名字の由来を解説。テニスの錦織選手の名字は古代の織物を指し、皇族の錦の織物を織る錦織部と呼ばれる職人集団から来ている。発祥は近江国(現在の滋賀県)で、現在も大津市に地名として残っているそうだ。
(ダイアプレス 815円+税)
「日本人のおなまえっ!①」NHK「日本人のおなまえっ!」制作班編
NHKの人気番組の書籍化。日本全国に175万以上いる「鈴木」さん。学校にも会社にも1人や2人は鈴木さんがおり、いたって平凡な名字というイメージだ。しかし、鈴木という名字には非常に謎が多いという。そもそも、“鈴の木”などあるのだろうか。
そのルーツをたどると和歌山県の熊野地方にたどりつく。海南市にある藤白神社には鈴木家系譜が伝えられており、初めて鈴木姓ができたのは900年代のこと。代々、米の収穫を神に祈る神官を職業としていた人が最初の鈴木さんだという。熊野地方の方言では、稲わらを積み上げたわら塚のことをスズキと呼んでいた。そこで、「鈴」と「木」の字を当てて、鈴木と名乗るようになったとか。
思わず誰かに話したくなる名字のうんちくが満載だ。
(集英社インターナショナル 1400円+税)