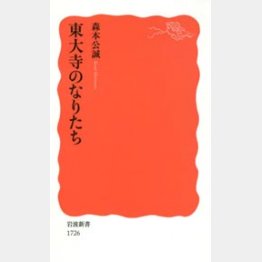「東大寺のなりたち」森本公誠著
著者は、2004年から07年まで奈良・東大寺の第218世別当、ならびに華厳宗管長を務めたことがあり、現在は東大寺長老である。ただ異色なのは、京都大学で学んだイスラム学者でもあることである。私は一度、著者の講演を聞いたことがあるが、東大寺の法華堂の修復工事から明らかになってきたことについて、理路整然と説明されたことに感銘を受けたことがある。
その経験があったので、さっそく本書を買い求めた。タイトルから予想されるように、東大寺がどのように生み出されたのかについて詳しく説明されている。さらには、東大寺の有名な大仏が造られてからおよそ100年後に、その首が落ち、その修復作業がどのように行われたかも詳しく説明されている。修復作業の功労者である木工忌部文山について、これまでは詳細が明らかになっていなかったらしい。
ただ、予想とは異なるのは、朝廷内部における抗争についてかなり詳しく述べられていることである。
そこには何より、東大寺の創建や大仏の建立が、聖武天皇の発願で行われたことが影響していた。それは国家事業であり、国家と深く結びついた僧侶の組織も関係するし、外交も関わっていた。大仏の開眼供養が行われた後には、朝鮮半島の新羅の国から大使節団が派遣された。
それ以前、新羅との関係は緊迫していた。それでも、新羅が朝貢という形で日本に屈するような態度をとらざるを得なかったのも、大仏建立の背景には「華厳経」の思想があり、新羅では、「華厳経」が広まっているため、日本の試みを無視できなかったからである。
現代では、宗教と政治は分けて考えられている。しかし、古代においては、両者は密接に結びつき、むしろ一体の関係にあった。だからこそ、国家の安泰を図るために大仏が建立されたわけである。
その分、東大寺をめぐって、朝廷内の政争が深く関わってくるわけである。とくに奈良時代末期から平安時代初めは、天皇の位を誰が継ぐかで深刻な対立が生まれた。本書を読んで奈良の大仏を拝んだなら、なんとしても平和な国家をつくろうとした聖武天皇の強い思いが感じられるかもしれない。
(岩波書店840円+税)