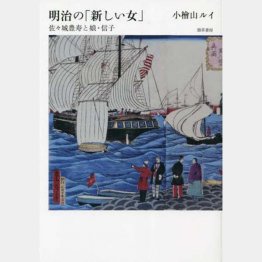「明治の『新しい女』」小檜山ルイ著
「明治の『新しい女』」小檜山ルイ著
「新しい女」とは、1911年に創刊された平塚らいてうをはじめとする雑誌「青鞜」によって女性たちを指す言葉として用いられた(当初はマスコミは揶揄的に使っていたが、らいてうはそれを逆手にとって「私は新しい女である」と宣揚した)。
佐々城豊寿とその娘・信子は、らいてうらに先立って旧弊な価値観から抜け出して「新しい女」として生きた。本書はこの母娘の足跡をたどりつつ、幕末から明治の歴史において女性とキリスト教がどのように関わってきたのかをマクロヒストリーとして描いたもの。
豊寿は、ペリーが来航した1853年、仙台藩の儒者・星雄記の五女として生まれた。幼い頃から漢学を修め、長じては男装し、馬に乗って仙台の街を疾走するという自由人だった。
維新後、東京に出ると、アメリカの女性宣教使に師事し、キリスト教と男女平等の思想に接する。その才能を認められ、東京女子師範学校の教師として招聘されるが、妻子ある佐々城本支との間に子どもができたため半年で辞職。その子どもが娘の信子だ。
豊寿はその後、禁酒・禁煙(後に廃娼)運動を掲げるキリスト教系の婦人矯風会の結成に参画するが、その歯に衣着せぬ言動は会に波風を立て内部紛争を引き起こした。
一方の信子は、矯風会のイベントで知り合った国木田独歩と知り合い結婚するが、わずか5カ月で離婚(その経緯は独歩の「欺かざるの記」に書かれている)。その5年後、婚約者の待つシアトルへ鎌倉丸で渡航中、船の事務員と恋に落ち婚約を破棄、「鎌倉丸の艶聞」としてマスコミに騒がれる(この事件を題材にしたのが有島武郎の「或る女」で、信子は主人公のモデル)。
女性は人前で自分の意見を言わないことが美徳とされていた時代に、周囲の目を気にせず自分の意志を貫いた母娘。2人が受けた誹謗中傷は現在の女性と無縁ではないことが突き刺さってくる。 〈狸〉
(勁草書房 5500円)