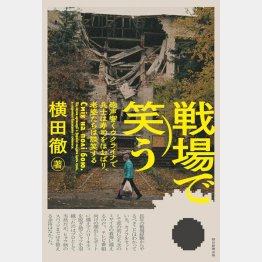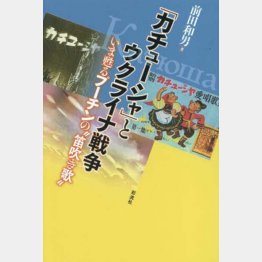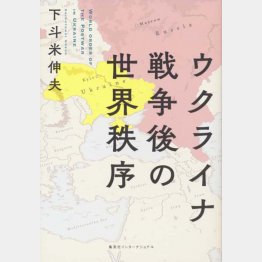ウクライナ戦争の深部
「戦場で笑う」横田徹著
トランプの大言壮語が空振りし、いよいよ混迷するウクライナ情勢。
◇
「戦場で笑う」横田徹著
戦争ジャーナリストの本はこれまでにも多々あるが、本書は最も素直に自分の弱さや失敗談をさらけ出した例のひとつだろう。
コロナ禍のブランクもあって実は内心乗り気でないまま始まったウクライナ取材。戦場で出会う面々もユニークだ。
現地の取材をセットするフィクサーは1日20万円を吹っ掛ける。ウクライナ支援のジョージア軍部隊に日本人義勇兵がいると聞いて出かけたら、相手は大阪ヤクザの組長の息子。いちばん頼りになるひとりは、なんとチェチェンやアゼルバイジャンなど南北コーカサス地方を研究する大学院生の日本人女性だったりするのだ。テレビ向けの顔出しリポート撮影ではハローキティのTシャツを脱いだものの下は「ヒョウ柄のスパッツのまま」なんてシュールな光景まで披露してくれる。
20代でカンボジア内戦を取材し、以後、インドネシア、東ティモール、コソボなど世界の紛争地を歩いてきた著者もいまや50代半ば。これまで九死に一生を得てきたものの、「手持ちの運は使い果たした」という自覚はあるらしい。そろそろ幼い娘さんのもとに帰ってあげてください、と声をかけたくなる好著。 (朝日新聞出版 2310円)
「『カチューシャ』とウクライナ戦争」前田和男著
「『カチューシャ』とウクライナ戦争」前田和男著
ロシア民謡といえば〈♪り~んご~の花ほころ~び~〉のカチューシャを思い出すという中高年は多いだろう。ところがこの元歌、なんとロシアでは軍歌としてはやったのだという。したがってウクライナ人はこの歌に強い拒否反応を示すのだそうだ。
これに気づいた著者は、その昔の「うたごえ喫茶」全盛期を知る団塊世代。日本では甘酸っぱい青春歌謡のように知られているが、もともとの歌詞は戦場に行った恋人を思う内容なのだ。
本書が興味深いのはそんな愛国歌謡がなぜ日本では青春の歌に化けたのか、という問題を通して、戦後の日本で共産主義に対する一般の認識がどう変わったのか、共産党側の宣伝戦略がどう関わったのかを追跡しているところだろう。
扱い方次第ではトリビアな話に終始しかねない話題を、この世代ならではの肌感覚で歴史的にたどっているのがいい。
元書評新聞の編集者だっただけに資料調べと当事者世代ならではの嗅覚がうまくかみ合った中身になっている。 (彩流社 2200円)
「ウクライナ戦争後の世界秩序」下斗米伸夫著
「ウクライナ戦争後の世界秩序」下斗米伸夫著
同じスラブ系でも、ウクライナとロシアの関係は一筋縄ではいかない複雑さらしい、というのは日本人でも知る常識。とはいえ複雑さの中身となると専門家の解説に頼るほかない。著者はソ連・ロシア研究のベテランとして知られた政治学者。新聞やテレビでもひところよく登場していた。
著者によると冷戦終結直後、ロシアとウクライナとベラルーシは三国最高首脳会議を開き、独立国家共同体を形成したが、実は条約締結の段階でロシア語訳とウクライナ語訳では国境に関する解釈が違っており、既に両国間には思惑の違いがあったという。日本の外務省もここに気づいていたそうだ。
著者はロシアの専門家らしく、一方的なロシア悪玉説、プーチン責任論に走らない。
むしろ冷戦後の欧米諸国、特にアメリカやイギリスの身勝手な対応に問題があったことを力説する。
あとがきでも「アメリカのネオコン系勢力の影響下」にあった欧州の歴代指導者たちの責任を問い、英ボリス・ジョンソン元首相と米バイデン前大統領を名指しで批判している。 (集英社インターナショナル 1980円)