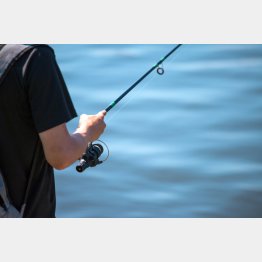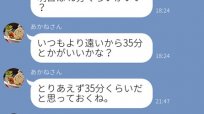「代官山のトレースだね」地元同級生からの“皮肉”が刺さる…“私は違う”と信じた女が虚飾に気付く瞬間【ある地方都市の女・根上朱里 32歳#3】
【ある地方都市の女・根上朱里 32歳#3】
【何者でもない、惑う女たちー小説ー】
都内から鈍行電車で2時間ほどの港町の故郷に朱里はUターンし、古民家を改装したギャラリーカフェをオープンする。しかし、知人以外の客は来ず苦戦する。妥協して地元客受けするメニューを出すことにする中、幼馴染の俳優が客としてやって来て…。【前回はこちら】【初回はこちら】
【関連記事】「世帯年収1500万じゃ恥ずかしい」御茶ノ水からの“都落ち”…武蔵小杉のタワマンを選んだ女のプライド【武蔵小杉の女・鈴木綾乃 35歳】
大輝の“意外な感想”に愕然
目の前に現れたのは、浜野大輝だった。願ってもない相手であった。
「どうしたの? 帰って来てるの?」
「いやぁ、帰ってきてるっつうか、最近オフは実家で釣り三昧なのよ」
彼はサングラスを取り、少し焼けた顔をクシャッと崩してぎこちなく微笑んだ。
「釣り…? 好きだったの?」
海に近いこの町であっても、仕事にしている者を除き釣りをする人間は意外と少ない。釣りやマリンアクティビティは観光客のものという認識だ。
「最近始めたんだ。ここ出身と言うと、釣り好きだって思われるからさ。静岡人がみんなサッカーをやっているって勘違いされがち、みたいな」
出来もしない釣り関係の仕事が来ることがあるという。だからいっそ好きになってしまおうということらしい。
「へぇすごいサービス精神」
「需要には応えないと。てか、ここで何やってんの? バイト?」
「ギャラリーカフェだよ。イラストレーターやっていたけど、Uターンして地域おこしではじめたの」
大輝は店内を見まわした。すると、力の抜けた笑顔を浮かべてつぶやいた。
「普通にありそうな店だね」
「へぇ。代官山や鎌倉あたりにも普通にありそうな店だね」
朱里はその言葉の意味を考える。微かにチクりとしたものを感じた。てっきり、手放しで褒めてくれるものだと思った。反発心で前向きにうけとる。
「オシャレだって言ってくれているんだよね」
「まぁ…」
ぎこちない表情を見て見ぬふりをして、勢いであの件を持ち掛けた。
「実はここでイベントを計画しているの。ちょくちょく実家に帰っているなら大輝に出てほしいんだ。大輝の事務所にも前、企画書送って…」
「そうなんだ、確認しとくわ」
目を逸らす彼に朱里は、それ以上言葉を交わすのが怖くなって、事務的に注文を尋ねた。彼はミートソースパスタを選ぶ。新メニューの業務用レトルトの食材のそれを。
大盛をぺろりと平らげ「うまかったよ」と感想を残し、すぐに店を出て行った。終始笑顔ではあったが、去ってゆく背中に冷たい温度を感じた。
信じられない朗報が舞い込む
それは、突然の連絡であった。
「ネガミさん、おめでとうございます。応募作品を、国際エンタテインメントフェスティバルのメインキャラクターに選定させていただきました」
開店して3か月。イベントの開催を諦め、相変わらずカフェは赤字状態の中でのこと。
3年後に開催される国を挙げてのイベントのコンペになぜか朱里の作品が通ったのだという。その募集は、東京にいた2年前に行われており、ダメ元で応募したものであった。
選考過程は逐一伝えられていたものの、期待しておらず、カフェ開店のバタバタもあり、全く気にしてもいなかった。寝耳に水とはこのこと。
――信じられない…うそでしょ??
うそでしょ?――突然、賑わいを見せるカフェ
そこからは、怒涛の日々であった。
記者会見、取材の連続。別件イラストの発注まで沸いて来た。
「お姉ちゃんはイラストの仕事に専念してよ。私、コーヒーくらいは出せるから」
理子のそんな言葉に甘えて、土日だけの営業にしてしばらくカフェの運営を任せることにした。どうせ客はほとんど来ない。育児中の彼女の息抜きにぴったりだと思ったのだが…。
「なにこれ!!」
東京での仕事が一段落つき、ひさびさに地元を訪れると、店内は多くの若いお客さんで溢れていた。
どうやら、報道で朱里の名が報じられ、この地のカフェ店主だと聞き付けた人々がこぞってやってきたのだという。理子だけで店が回るわけはなく、家族総出で出動しなければいけないほどにぎわっていた。
「昨日なんてね、お姉ちゃんのお友達のアート作品が売れたの。10万円もする、あのへんなオブジェ。あと、お姉ちゃんがスケッチした海の絵も」
忙しそうにレモネードをグラスに注ぐ妹の姿。そしてそれをおいしそうに飲むお客さん。作り置いたスパイスカレーも業務用食材も、完売御礼だった。
「もしかして、ネガミ先生じゃない!?」
「地元の誇りです!」大輝の言葉を思い出す
どこからか声が聞こえてきた。なにげなく店のフロアに姿を見せると、歓声と拍手が朱里を包む。
「おめでとうございます! 地元の誇りです!」
「あ、え…ありがとうございます…」
笑顔と祝福で胸がいっぱいになる。戸惑いと共に、自分がここにいることで、これだけの人が集まる現実を目の当たりにする。
――ど、どうして??
「地元の誇りです!」大輝の言葉を思い出す
その時、このカフェに欠けていたものがわかったような気がした。
朱里は思い出す。大輝がここに来た時に言われた言葉を。
――代官山や鎌倉あたりにも普通にありそう――
所詮この場所は、東京や湘南のトレースだったのだ。おしゃれに見えるだけで、個性も信念も何もなかった。つまり、有名アニメを使った町おこしやチェーン店と、客観的にはなんら変わらなかった。
あがいても20代のうちに東京で成功できなかった自分。心が折れる中で、都落ちする理由が欲しかった。地元で、東京にいた感度の高い自分というアイデンティティを示したかった。
根本は、そんな下心で作った居場所だった。ここが、カルチャーやアートがなにもない場所だと見下すことで、都会かぶれの自己顕示欲を満たしたかった。
そもそも自分は地域おこしなんて、興味はなかったのかもしれない。
大輝はそこを見透かしていたからこそ、あの言葉で皮肉ったのだ。結局、地元で大きい顔をしたいだけの松波のおじさんと変わりなかったんだ。
「くそダサい」と言った自分を悔む
朱里は、東京に再び居を構え、2拠点生活を始めることにした。
カフェ運営を妹に任せ、オーナーとして携わりながら、もう一度イラストレーターとして、改めて勝負してみる。
地元で東京の真似事をするより、地元の人間が広い場所で活躍して、その存在を知らしめることが本当の地域おこしだと気づいたのだ。
――私は、この町のことを、何も知らなかったんだ。
大輝がいきなり釣りをはじめたのも同じこと。最近、彼は個人YouTubeで、釣りチャンネルをはじめ、地元の海の素晴らしさを語っているらしい。自分本位でない、地域への影響の起こし方をわきまえていると思った。
東京へと向かう、東海道線の駅のホームで、ちらりとアニメ絵の看板が朱里の目に入った。
「あの美少女アニメ、ちょっと見てみようかな」
さっそく鈍行列車で2時間。その世界に浸ってみる。意外とすぐにハマってしまった。
どおりでアニメを見た観光客がこぞってくるはずだ。自分の目には見えていなかった、地元のいいところがたくさん詰まった作品だった。
かつて、この町を「くそダサい」と評したことをたまらなく悔いた。
Fin
(ミドリマチ/作家・ライター)