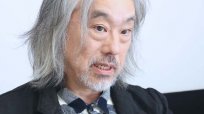(4)家畜やペットが感染源に…日本の備えはどうなっているのか
日本でも対策が進んでいて、今年4月には国立感染症研究所と国立国際医療研究センターが統合し、国立健康危機管理研究機構(JIHS)が発足。一般的に風邪とされる呼吸器感染症が感染症法上の5類に分類され、監視対象となった。すでに1月には長崎大学のBSL-4(バイオセーフティーレベル4)施設が厚生労働大臣から施設認定され、エボラウイルスのような危険な病原体の取り扱いが可能になった。長崎大学感染症研究出島特区ワクチン研究開発拠点拠点長の森田公一同大教授が言う。
「こうした動きは、新たなパンデミックに備えるためです。ネクストパンデミックは、今や『ある、なし』ではなく、『いつ発生するか』の問題なのです」
この拠点では、新たな感染症が出現してから100日以内でワクチンを開発・実用化する国際的な取り組みである「100日ワクチン構想」に対応する体制づくりが進められているほか、長崎大独自の技術を使った重症熱性血小板減少症候群ワクチンの開発などが行われている。
とはいえ、日本で13万人の命が失われた新型コロナの教訓が十分生かされていない面も残る。全国の保健所からの感染症情報がFAXで送られるため、リアルタイムでの情報収集が困難。さらに米国がトランプ政権下でWHOからの脱退を表明しパンデミック条約の採択にも参加しなかったため、国際的な枠組みの実効性に懸念が残る。
個人レベルでは、免疫力維持のための睡眠・栄養・運動、信頼できる情報源からの最新情報収集、手洗い・うがい・マスクの適正使用、咳エチケットなど基本対策の習慣化が求められる。それを日常生活に定着させることが、自身や周囲を守る第一歩となる。 =おわり