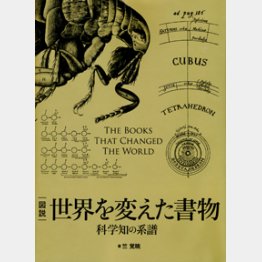「世界を変えた書物」竺覚暁著
15世紀半ば、グーテンベルクによって活版印刷技術が発明されるや、瞬く間に各地に伝播し、印刷所が次々と造られていったという。それほどに、人々は知識を伝え、受け取ることに飢えていたのだろう。印刷技術の確立は書物の普及に貢献し、人類のその後の発展を加速化させた。本書は、中でも科学技術の発明、発見を記録し、その分野の更なる進展を刺激した画期的な書物100冊の初版本を集めて紹介する稀覯本写真集。
ヨーロッパの科学知発展の系譜は、古代ギリシャやヘレニズム世界の知の継承から始まった。まずはその継承を担ったアリストテレスの「ギリシア語による著作集」(初版1495年)をはじめとする貴重な「インキュナブラ」(グーテンベルクの発明から1500年までに印刷された書物)を紹介。
アリストテレスの自然学や宇宙論を収めた同書には、この書物のために特別に鋳造されたギリシャ文字の活字が使われているそうだ。
同じく1482年初版のエウクレイデス著「幾何学原論」は、すべての幾何学の礎の書。そう、エウクレイデスとはユークリッドのこと。本書の余白には幾何学図形が添えられており、本文と図形を同時に記載するこの表現法が、その後の科学技術書のスタイルを決めた。
ユークリッド幾何学をはじめ、古代の学術的知識はローマ帝国の滅亡とともに失われ、ヨーロッパには伝わらなかった。しかし、その一部が写本でアラビアに伝えられ、9世紀以降、アラビア語文献がヨーロッパに伝わりラテン語に翻訳された。それらがさらに活版印刷技術の実用化によって広く普及したという。
以後、科学技術史上最大の書物のひとつといわれるニコラス・コペルニクスの「天球の回転について」(1543年)や、万有引力や流体力学など古典物理学を確立したアイザック・ニュートンの「自然哲学の数学的原理(プリンキピア)」(1687年)、複合顕微鏡を考察、製作してミクロの世界を観察して細胞を「Cell」と名付けたロバート・フックの「微細物誌」(1665年)、放射線を発見したウィルヘルム・コンラッド・レントゲンの「新種の輻射線について」(1895年)、そして「一般相対性理論の基礎」(1916年)をはじめとするアルベルト・アインシュタインの一連の書まで、知の巨人たちによる名著が勢ぞろい。
それぞれの書籍の生まれた経緯や果たした役割も解説。さらに見開いた中の様子はもちろん、上横表裏の4方向から装丁を撮影した写真や、素材、サイズなども紹介され、愛書家、収集家の心をくすぐる。
科学の歴史と発展を一望するこの書物の数々は、すべて金沢工業大学ライブラリーセンターの収蔵品だという。これほどのコレクションが日本にあったことに驚くとともに、実物を目にする日もくるのではないかと期待が湧く。(グラフィック社 2500円+税)