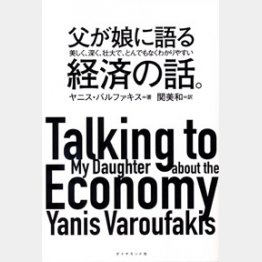「父が娘に語る経済の話。」ヤニス・バルファキス著/ダイヤモンド社
著者は、最近世界で注目を集める「反緊縮」運動の旗手だ。2015年にギリシャの財務大臣に就任し、財政緊縮化を求めるEUの要求を敢然と拒否して、大幅な債務の棒引きを要求したことで名を馳せた。その著者が、娘に分かりやすく経済の仕組みを話したのが本書だ。
本書は、「なぜ世の中には、とてつもない格差が存在するのか」という疑問から始まる。その仕掛けを神話や戯曲、寓話を交えて、語っていく。もちろん、ここの部分も平易で素晴らしいのだが、本書の圧巻は4章以降の金融と労働を扱った部分だ。この2つの市場では、一般の経済学が成り立たない。例えば、一般の経済学では売れ残りは発生しない。売れなければ値段が下がり、需要が喚起されて、全部売れると考えるからだ。
しかし、労働者は食べていかなければならないから、二束三文で労働力を売ることはできない。また雇う側も、賃金が下がったからといって、雇う人数を増やそうとは、必ずしも考えない。賃金が下がって購買力が落ちれば、ビジネスの売り上げが減って、人を雇う余裕がなくなるからだ。
金融市場も、事情は同じだ。金利が下がるのは、不況のシグナルだから、安い金利が借り入れを増やすとは限らないのだ。
著者の景気拡大策は、政府が赤字を出して公的債務をつくることだ。財政を拡大すれば、需要が生まれて雇用は拡大する。同時に、政府が借金をすれば、銀行も資金の運用先が得られる。だから、公的債務は決して悪いものではないというのだ。
ケインズが世界恐慌に苦しむ世界をみて、ケインズ経済学を生み出したのと同様に、著者もギリシャ経済の苦境をみて、反緊縮の経済学を生み出したのではないだろうか。
日本は、アベノミクスによって、金融緩和策が採られて、最悪のデフレ状況からは、脱出することができた。しかし、アベノミクスは、財政は緩和しなかった。むしろ消費税増税で、さらなる引き締めに出ようとしている。
著者は金持ちが好む緊縮策を転換するためには、民主化が必要だと説いている。ただ、その前提として、国民が経済学を理解していなければならない。本書はその第一歩を踏み出すための教科書だ。 ★★半(選者・森永卓郎)