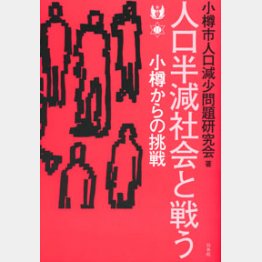人口減少社会
「人口半減社会と戦う」小樽市人口減少問題研究会著
新生児が減り、若者が減り、人口が減って、このまま日本は滅ぶのか。
◇
北海道の小樽といえば、運河沿いの歴史的建造物が観光資源として有名。昨年の「地域ブランド調査」(ブランド総合研究所)でも自治体の魅力度ランキングで4位に輝いている。
ところが、その小樽が1964年の人口20万人をピークに、近年では毎年2000人のペースで人口が急減。今年7月末現在で11万5000人と、ピーク時の半分になっているのだ。危機感を抱いた小樽市と地元の小樽商科大学が組んで研究会を設置。その最終報告が本書だ。
小樽から快速で30分の大都市・札幌。その近郊は人口増加を続けているのに、なぜか小樽は減少中。その理由を探って、本書は歴史的な背景から産業構造の変化、所得と人口動態の関係、さらに現在の札幌近郊と小樽の住民の意識調査などへと踏み込んでいく。なんでもかんでも少子高齢化のせいにせず、固有の原因をつきとめ、対策を講じようとする姿勢は学ぶところ大。
(白水社 2200円+税)
「孤立する都市、つながる街」保井美樹編著
孤独死や自殺が当たり前になってしまった今日。どこかでそれが起こると、その街(あるいはマンション)は、問題を解決しようと住民たちが立ち上がるどころか、みなで黙って知らんぷりで事件を隠そうとする。でないと街の悪いイメージが知れ渡り、資産価値に響くからだ。
人口減少は、単に新生児が少ないという以上に、コミュニティーの希薄化が進み、社会全体が活力を失い、若者たちが未来に希望を見いだせず、その日暮らしの小さな視野しか持たなくなるのだ。
本書は都市問題やまちづくりに関する各分野の専門家を主軸に、若者の就労支援や事業開発、未来社会デザインなどの実践活動を行う団体の主宰者らが集まった論集。各章とも豊富な事例を紹介し、未来を切り開く意欲を感じさせる。
(日本経済新聞出版社 1800円+税)
「人口減少 社会のデザイン」広井良典著
産業革命以後、工業生産力と植民地支配でグローバル化を牽引してきたイギリスがEU離脱という決定をしたのは、「グローバル化の終わり」が始まったということである。この先には2つのベクトルがあり、ひとつはトランプ政権のような、強い「拡大・成長」志向や利潤極大化、排外主義のナショナリズム的な方向である。もうひとつはドイツ以北のヨーロッパにみられる、ローカルな経済循環やコミュニティーから出発して、ナショナル、グローバルへと成長させ、「持続可能な福祉社会」を志向する方向である。日本はアメリカに近いが、歴史的に「持続可能な社会」を重視してきた伝統がある。「持続可能な社会」を目指すための10の論点と提言。
(東洋経済新報社 1800円+税)