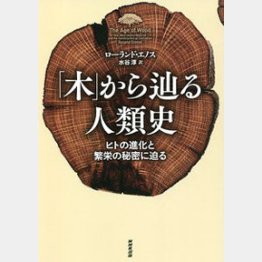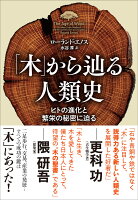「『木』から辿る人類史」ローランド・エノス著 水谷淳訳
人類の文明は、石器時代、青銅器時代、鉄器時代の順に発達を遂げてきたというのが定説とされてきたが、ここには肝心な素材が抜けている。木材だ。著者はいう、「私たちの進化と文化の長い歴史に連続性を与えているのは、ほかならぬ木という素材だ」と。さらに「樹木中心的な見方で世界を見渡せば、私たちが何者で、どこからやって来て、どこへ進んでいくのかを、ずっとはっきりとらえられる」とも。
この言葉に偽りなく、本書は木と人類の関わりを根源的に描いていく。まずは二足歩行と木の関係。樹上生活をしていた人類の祖先は、手で高いところの枝をつかみながら複数の枝に体重を分散させて移動することを覚える。この動きは二足歩行に適した体をつくるとともに、枝の曲がりにくさを的確に予測するという知能を発達させることにもなる。
やがて地上へ降りると、木を燃やして火をおこすことで敵の襲撃を防ぎ、煮る・焼くという調理技術によって食料の幅を広げていく。またサバンナの植物の根茎を掘り起こすには木製の道具が必要だったし、石器が登場しても、石のもろさに比して圧縮力と張力に優れている木はさまざまな道具を生み出した。こうした木材の高い汎用性は青銅器、鉄器の時代でも威力を発揮していく。
さらに目を開かされるのは、ヨーロッパでは石造建築が主流のように考えがちだが、石造建築の肝心な細部を支えているのは木材だということ。またイギリスの有名な石器時代の遺構、ストーンヘンジもその大部分は木造だった可能性があるとも示唆されている。産業革命時代に至っても木は橋や船といった主要な構造物の素材として使われていた。木に代わって鉄が使われるようになったのは、加工しやすい錬鉄が発明された19世紀末になってからだという。
木の役割で最も大きいのは、森林が二酸化炭素を吸収して酸素を生み出すことだ。その関係が現在危機に瀕(ひん)している。最終章の木と人間の関係を修復するための提言は極めて重要。環境問題の教科書としても読める好著だ。 <狸>
(NHK出版 2530円)