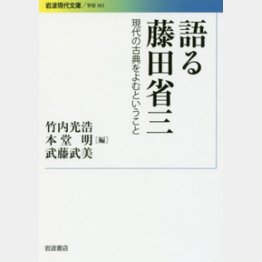思想家・藤田省三の批判精神の楽屋裏
「語る藤田省三」竹内光浩・本堂明・武藤武美編 岩波現代文庫 1400円+税
1960年代末~70年代初頭の大学闘争のときに、大学当局の対処の仕方に抗議して、自ら大学を去った、あるいは大学から追われた学者たちがいた。
たとえば、同志社大学の哲学者・鶴見俊輔、国際基督教大学の新約聖書学者・田川建三、そして法政大学の思想史家・藤田省三である。藤田は71年に大学を去り、80年に復職するまでの約10年間の「浪人時代」に、法政大学の卒業生を相手に、自宅で研究会を開いていた。本書の第Ⅱ部にはそのときの研究会の記録が収められている。Ⅰ部は、大学を辞める直前の講義記録、Ⅲ部は復職直後の講演録という構成である。
丸山眞男に師事し、天皇制論の古典「天皇制国家の支配原理」をはじめ、「維新の精神」や「精神史的考察」といったラディカルな批評をなしてきた藤田の文章は密度が濃く、それがまた心地よい緊張感をもたらした。本書は表題通り、講義・講演などの語りを起こしたもので、ことに研究会の記録は、教え子の発表を受けてのコメントであるから、文章ではうかがえない思想家・藤田の楽屋裏がのぞけるようで興味深い。
内容は多岐にわたる。森鴎外「現代思想」、尾崎翠「第七官界彷徨」、ジョイス「若い芸術家の肖像」、ベケット「ゴドーを待ちながら」、ブレヒト「ガリレイの生涯」、荻生徂徠「政談」……。
それらを語りながら藤田が強調するのは、書かれたものの歴史的文脈を見据え、既存の概念や通説にとらわれずにそのテキストの神髄を見極めることだ、と。そうした藤田の姿勢は、冒頭の「現代とはどのような時代か」によく表れている。
半世紀前に語られたコミュニケーション論であるが、空間が狭まることで価値の多様性が失われると指摘しており、インターネット時代の今日の状況をも刺し貫くその射程の深さに目をみはらされる。そうした藤田の批評精神が、アカデミズムの外で継承されていたことに感動を覚える。
<狸>