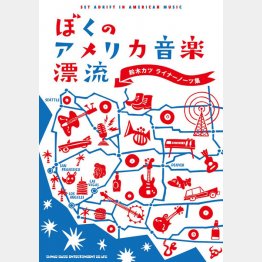ディランが時代のアイコンになり得たわけ
「名もなき者」
先週末封切りの「名もなき者」はボブ・ディランのデビュー時代を描いた話題作。事前にネットやTVでディランの若いころの記録動画が出回ったが、改めて聴くとほんとに下手。声量もなく、この貧相な若者に時代が熱狂した理由はいま理解されるだろうか。今回の映画は、そんな彼の“何がよかったのか”を現代にわからせることだろう。
1961年、「フォーク・リバイバル」ブームの中心になったニューヨーク。ミネソタの田舎から出てきた若者が、偶然の機会を得て期待の新星になっていく。実存主義とビートニクスがはやった当時のニューヨークの、デカダンきどりだがこぢんまりと居心地のいい感じがよく描けている。かつてのニューヨークは文学も音楽も美術も写真も、それぞれ小さな部族に分かれて共存していたのだ。
主演のティモシー・シャラメは本物よりずっと洗練されて、素朴だがきらめく詩心を持った若者を、女たらしの部分まで含めて巧妙に演じる。ここまでやって初めて、ディランが時代のアイコンになり得たわけが伝わるのだろう。
特筆すべきはピート・シーガー役のエドワード・ノートン。最初は彼とわからないほど自然に、フォーク界の人格者の像を丹念に描き出した。本作の成功のかなりの部分が実は彼の功績だ。
劇中、悪者めいて描かれるアラン・ローマックスが少々気の毒。全米を歩いてアメリカ音楽史の人種と風土の多様性を丹念に採譜した功労者だった。
ロナルド・D・コーエン編「アラン・ローマックス選集」(みすず書房)は「ルーツ・ミュージック」と呼ばれるフォークやカントリーやブルース等々の原形を訪ね集めた貴重な論集だが、あいにく絶版。代わりに鈴木カツ著「ぼくのアメリカ音楽漂流」(シンコーミュージック 2420円)を薦めたい。マニアならではの愛情あふれるライナーノーツ集である。 〈生井英考〉