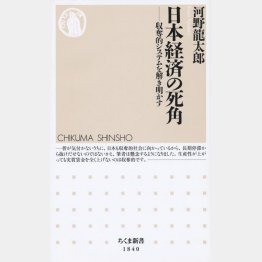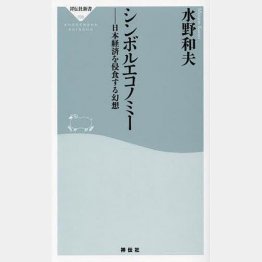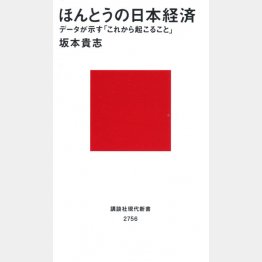日本経済はどうなる
「日本経済の死角」河野龍太郎著
トランプの顔色をうかがいながらの石破政権。一向に抜け出せない日本経済の衰えをどうする?
◇
「日本経済の死角」河野龍太郎著
「失われた30年」の主因だったデフレは解消されたというが、暮らしはまるでよくならない。それは単に目先の景気の話ではなく、長年かけて蓄積された日本経済のゆがみの構造に由来するのではないか。
本書は大手都銀から投資コンサルへ転じたベテランのエコノミストが読み解く日本経済の危機的状況の解説だ。
現在の日本経済は、生産性が上がっても実質賃金が上がらない。アベノミクス時代から株価は上がっても経済成長率は低いままという状態を続けていた。結果として日本社会では経済格差が広がるばかりだ。金融緩和に代表されるマクロ経済政策が足りないため経済停滞が起こるというのはアベノミクスの主張。これを安倍政権の後の岸田政権でも踏襲し、国民の信任は得られなかった。いまやアベノミクスの誤りは証明済みだ。日本はすでに途上国ではないため、確実に成長を高める理論的モデルはない。
こうした現実をふまえ、著者は日本経済が「衰退する国家」の「収奪的」なシステムの犠牲になったという。かつて1億総中流ともいわれた「包摂的」な日本経済は、いま、「収奪」のそれに変わった。その現実を見据えたリアルな経済論だ。 (筑摩書房 1034円)
「シンボルエコノミー」水野和夫著
「シンボルエコノミー」水野和夫著
証券会社から内閣官房を経て大学へ。さまざまな場で実体経済に関わってきた著者が本書で問題にするのが「日本経済を侵食する幻想」(副題)。驚くのは巻頭の「はじめに」で披露されるテーマ。前衛演劇の例を引き合いに、21世紀の世界は「幻想」に侵された「病院」のようなものだというたとえ話から、現代の資本主義は「リアルエコノミー」(現実経済)から「シンボルエコノミー」(幻想経済)に移行したというのだ。マスコミなどでは何十年ぶりの株価高値更新と報じるが、実はそれは「人々を無意識のうちに『日本という幻想』に押し込めて」いるという。
1982年、バブル経済の発生の前に資本移動と為替と金融のシンボル経済が財とサービスの流れによる実物経済(リアルエコノミー)に取って代わった。リアルとシンボルが同じ率で上下しているときは問題はない。しかし後者が大きくなると人は株価や金の価格を見て経済環境が好調であるかのように思い込むのである。
単なるアベノミクス批判にとどまらず、バブル時代からの現代史をふまえた刺激的な経済論だ。 (祥伝社 1100円)
「ほんとうの日本経済」坂本貴志著
「ほんとうの日本経済」坂本貴志著
物価が上昇基調に転じ、いよいよデフレ脱却の期待が高まった日本。ところが経済新聞は「株価高騰」「日本経済復活」をうたうものの、日々の暮らしは厳しくなるばかり。物価情報は人々の実質賃金を押し下げ、資産価値の上昇や日本円の減価も一部の大企業製造業や資産家を潤すだけ。毎日の通勤電車でも人々の表情は明るくなどなっていないのだ。
それでも経済全体を見れば、女性や高齢者の賃金労働の場は増加し、長時間労働も減ってはいる。要するに以前と比べると、より短い労働時間でかつてと同じぐらいの賃金を手にしている人の数は増えているわけだ。それでも人々の心は明るくなったとはいえず、実体経済はなるほどダイナミックに変化しているが、その実感が得られないという矛盾がある。
背景にあるのは少子高齢化による人口の減少。これによる日本経済の構造転換に社会や政治が対応していないと著者は指摘する。
この問題を論証するために本書では山形県酒田市などの事例を基に、人口減少の影響をいち早く受ける地方の中小企業に焦点を当て、近年の経済環境の変化を具体的に読み解いていく。著者は厚労省から内閣府のエコノミスト、そして民間シンクタンクに転じた今年40歳の第一線アナリスト。
(講談社 1100円)