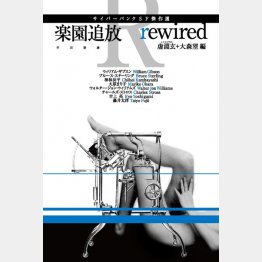意思と肉体を持ったAIが現実世界で動き出す
「トロン:アレス」
興行上の失敗作がやがて人気を得てカルト映画化するというのはよくある話。典型が「ブレードランナー」だ。同じ1982年に全米公開されてやはりコケたのが「トロン」。ゲーム制作者がゲームの中にのみ込まれてレースを戦うSFだが、初の実写とCGの本格的合体があえなく失敗。それが約30年後に復活し、さらに15年後の今年、第3作が登場した。先週末封切りの「トロン:アレス」である。
シリーズ物というには間が空き過ぎているが、それゆえの興味というか、たぶん意図せざる面白さが生まれた。40年超の年月を経て当初はトンガっていた物語の味つけが大衆の舌になじみ、チェーン店なみの域に達したのだ。
これは悪口ではない。現に本作では電脳空間のAIが意思や感情を抱き、肉体まで持って現実空間で動く。逆に生身の人間も簡単に電脳コードに書き換えられ、AIと人間はためらいなく互換的に描かれる。昔ならそれなりの理屈が必要だった設定が、本作ではいとも気軽で達者なポップコーン・ムービーになっているのだ。筆者など年のせいか近ごろの映画の暴力描写が苦手なのだが、本作のバリバリドッカンはあとくされなく、しかしチャチでもない。本当はとんでもなくダークな話のはずなのに、さすがディズニー、まことにあっさりとファミリー向け娯楽編に仕立て直しているのである。
思い出すのがサイバーパンク小説。「トロン」第1作と同年のW・ギブスン「クローム襲撃」で幕を開けたSF界の反逆児だが、虚淵玄・大森望編のアンソロジー「楽園追放 rewired」(早川書房 902円)では、イキったパンク少年が30年間で半グレの弁護士なみに世慣れてゆくような過程がわかる。いまとなっては昔の「トロン」の安っぽくプラスチッキーな手触りが懐かしいなどと思うのはヘソ曲がりでしょうか。 〈生井英考〉