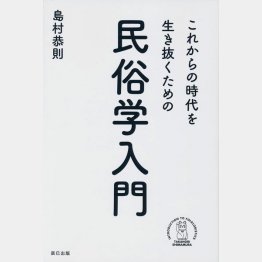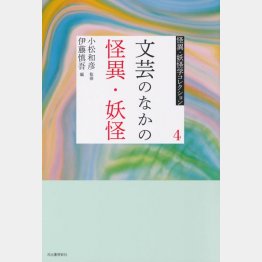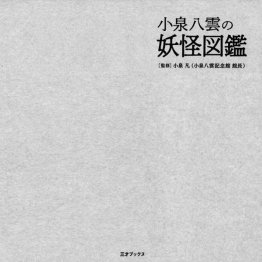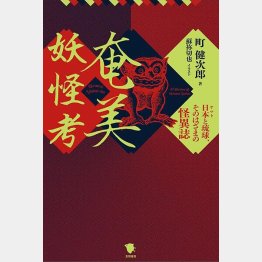民俗学的視点でのぞく日本の怪異・妖怪の世界の本特集
「これからの時代を生き抜くための民俗学入門」島村恭則著
9月29日からスタートしたNHK連続テレビ小説「ばけばけ」。民俗学的視点で日本の文化や怪談を愛した小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と、その妻セツがモデルの物語だ。そこで今回は、日本の民俗学や怪異、妖怪を考察した4冊を紹介。この機会に、日本のユニークで奥深い世界観をのぞいてみては。
◇
「これからの時代を生き抜くための民俗学入門」島村恭則著
民俗学の世界では、人の生き死にに“霊的なもの”が深く関わるとされてきた。例えば妊娠では、霊魂が人体に入ってはじめて「人間」になると考えられてきた。神奈川県の三浦半島には、「子産み石」と呼ばれる丸い石が集まる海岸があり、女性がこの石をそばに置くと子どもを授かると信じられてきた。
実は日本各地の海岸部には、海から霊魂がやってきて丸い石に宿るとする信仰が数多く存在する。海の向こうは霊魂で満ちており、民俗学ではそうした超自然的な場所を「異界」と呼んで畏敬の念を抱いてきた。また、霊魂は7歳ぐらいまでは体の後ろから抜けやすいとされ、防止するため藤の蔓に餅を通して首にかけるなどの風習が今も残されている。現代では七五三は子どもの成長を祝うものとされるが、民俗学的には抜けやすい子どもの霊魂を補強する機会だと解釈できるという。
日本人の行動や感覚の根幹が見えてくる民俗学の入門書だ。 (辰巳出版 1760円)
「文芸のなかの怪異・妖怪」伊藤慎吾編、小松和彦監修
「文芸のなかの怪異・妖怪」伊藤慎吾編、小松和彦監修
気鋭の怪異・妖怪研究者たちによる論文を厳選したアンソロジーである。
顔の崩れたお岩さん、夜な夜な皿を数えるお菊さんなど、著名な幽霊はほとんどが女である。これはいったいなぜなのか、多くの研究者たちが考察してきたテーマでもある。
女の方が執着心が強い、封建制度で抑圧された怨念は女の方が強いなどの推論もある。しかし、怨霊と化した人間の歴史は、長屋王、菅原道真、崇徳院など男性の方が主流だ。本書では、幽霊画が「九相図」を手本に生まれたからではないかと仮定する。
「九相図」は人間の死体が腐敗して骨になるまでを9段階に分けて描いた仏教絵画で、奈良時代には日本に伝わっていたともされている。そして、「九相図」に描かれる死者は、ほぼ100%が女性だった。そのため、幽霊画は女性が多いと考えられるという。
ほかにも、日本で広がった「狐火」や、「土蜘蛛」と呼ばれた人々の正体など、“怪異”という日本の文化を深掘りしていく。 (河出書房新社 3520円)
「小泉八雲の妖怪図鑑」小泉凡監修
「小泉八雲の妖怪図鑑」小泉凡監修
八雲の代表作「怪談」のなかでも有名な“雪女”は、東京在住中に女中から聞いた奥多摩地方の伝説にインスピレーションを得たもの。実は、もともとこの伝説に雪女は登場しなかったが、美しい短編芸術にすべく、八雲がアレンジを加えたという。
日本語の読み書きができない八雲が、このように、伝説や昔話を新たな物語として語り直す“再話文学”を確立するためには、妻・セツの存在が欠かせなかった。「怪談」の原典の多くは、セツが浅草や神田の古本屋を巡って探し集めたもので、その資料を臨場感たっぷりに八雲に語ったという。妻としてのみならず、創作のアシスタントとしても大きく貢献したのだ。
八雲直筆の妖怪など貴重な資料も満載。怪異に魅せられた作家のまなざしをたどる。 (三才ブックス 2200円)
「奄美妖怪考」町健次郎著、蘇袮切也イラスト
「奄美妖怪考」町健次郎著、蘇袮切也イラスト
鹿児島県と沖縄本島の間に連なる奄美群島。日本と琉球の文化が重層しつつ島ごとに独特の文化があり、怪異もほかの地域にはない世界観が醸成されている。本書では、郷土史や言い伝えをもとに、「ムン(ムヌ)」と呼ばれる奄美群島の怪異世界をひもといている。
「ユナゥワ(夜の豚)」「クビキリャワ(首切れ豚)」「ミンキラウヮー(耳切れ豚)」。これらはすべて子豚の姿をした妖怪だ。子豚なら怖くはなさそうだが、夜道で股の間をくぐられた人は死んでしまうというから恐ろしい。
その正体は、赤子の霊だという。かつて奄美群島では、幼い子どもが死ぬと軒下に埋められていた。その霊が再生を狙い、股をくぐって母体内に戻ろうとする行動だと考えられている。山奥や海辺ではなく集落に出現するという特徴も、敷地内に子どもの亡骸を埋めていた地域性を反映している。
全国的にまだ知られていない、奄美群島の怪異の世界をのぞいてみては。 (笠間書院 2090円)