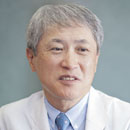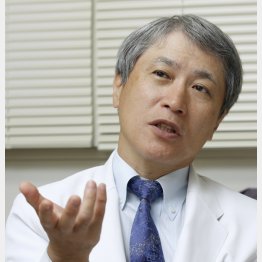心臓にとっては「安静」よりも「適度な運動」が大切になる
また、手術によって心臓の症状が改善して発作も現れず心機能も戻った患者さんであれば、手術による負担で弱っている全身状態を見極め、状態を引き上げながら負荷の程度を判断していきます。いずれの場合でも、その患者さんにとって問題ない負荷の程度を決定するのは、心臓リハビリの専門医の重要な仕事です。
患者さんの状態によって異なりますが、一般的に「負荷をかけ過ぎない=適度な運動」というのは、心拍数が130を超えない範囲が目安です。この数値は、最大負荷のひとつ手前に当たる「亜最大運動負荷」と呼ばれています。心臓手術を受けた患者さんやトラブルがある人は、この亜最大負荷を超える運動をしないような慎重さが必要なのです。
先ほども少し触れましたが、心臓にトラブルがあるからといって、体を動かさずにずっと安静にしていると、全身の筋力が低下して最終的にはフレイルと呼ばれる虚弱状態になり、寝たきりにつながるリスクがあります。
フレイルを避けるために、とりわけ重要なのが「歩行」です。ふくらはぎなどの足の筋肉は「第二の心臓」といわれています。足の筋肉は動くことによって心臓からの心拍出を受け入れています。また足の筋肉は、下半身を巡った血液を再び心臓に戻すポンプの役割も担っています。足の筋肉が衰えると十分に血液を戻せなくなり、静脈圧が高くなります。するとうっ血という状態になって、身体活動が抑制されたり、栄養を十分に取れなくなったりして、身体の恒常性維持にとってマイナスになる要素が増えてしまうのです。ですから、心臓リハビリの基本も「歩く」ことで、患者さんの回復度合いに合わせて少しずつ負荷を増やしていきます。