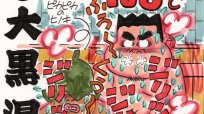「利他」の落とし穴とブームへの懸念 伊藤亜紗氏に聞いた
伊藤亜紗(東京工業大学 未来の人類研究センター長)

新型コロナ禍で「利他性」「利他的な行動」といった概念がちょっとしたブームだ。クラウドファンディングなどの寄付が増え、他者の利益を優先する考え方に関心が高まる。とはいえ、「利他」はけっして「利己」の対義語ではないし、そこには自己責任論や分断が蔓延する社会を打開するヒントとともに落…
![]() この記事は有料会員限定です。
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り3,354文字/全文3,495文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
今なら!メルマガ会員(無料)に登録すると有料会員限定記事が3本お読みいただけます。