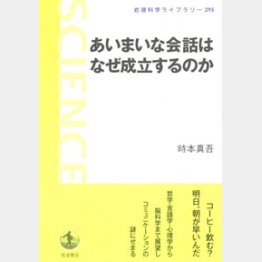「あいまいな会話はなぜ成立するのか」時本真吾著
夕食後の夫婦の会話。 妻「コーヒー飲む?」
夫「明日ね、出張で朝が早いんだ」
妻はコーヒーを飲むか否かを尋ねているのに、夫は飲む(イエス)とも飲まない(ノー)とも言っていない。それでも妻は、夫はコーヒーを飲まないのだと理解するだろう。なぜなら、夫の言葉には「コーヒーを飲むと眠れなくなるので、飲んでしまうと朝早く起きられない」という文脈が含まれていて、それを妻は理解したからだ。
日常の会話ではA=B、B=C、従ってA=Cといった論理的な言い方はせず、先の夫婦のようなあいまいな会話をしているケースが多いが、それでもさほど不都合なことなく会話が成り立っている。考えてみれば不思議だ。
本書は、あいまいな情報の中からどうやって適切な文脈を探し出し、決定できるのかについて、哲学、言語学、心理学、脳科学などさまざまな知見を引きながらその謎に迫っている。相手の言っていることの文脈を的確に掴むためには推論が必要だ。それがどのような場所で交わされたのか、周囲に他の人がいるのか、その他、天気や時刻、季節、相手の表情や服装、声のトーン、持ち物、さらには相手と自分の関係、共通の記憶等々、文脈の可能性は無限といってもいい。それを瞬時に判断するのだから、スーパーコンピューター並みの能力が必要となる。
それでも間違うことは多々ある。例えば先輩の男性から「ライブのチケットが2枚あるんだけど」と声を掛けられた女性は、デートに誘われたと思って即座に返事ができない。実はその先輩、恋人と一緒に行くつもりが都合が悪くなったので2枚ともあげるつもりだったのだ。とはいえ普段の先輩との接し方、後輩の先輩の評価などいくつもの変数があり、彼女の推論が間違いとは言い切れない。
これらの推論の過程を含めて、著者は会話というコミュニケーションの不思議を丁寧に解いていく。ごく当たり前だと思っていることも、このようにいったん疑問の俎上(そじょう)に載せてみると、さまざまな不思議が生まれてくる。これぞ学問の醍醐味だ。 <狸>
(岩波書店 1200円+税)