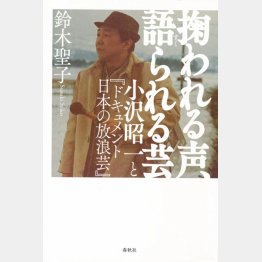「掬われる声、語られる芸」鈴木聖子著
「掬われる声、語られる芸」鈴木聖子著
新劇出身の個性派俳優・小沢昭一は、不惑を迎えた1969年に、著書「私は河原乞食・考」を刊行した。特出しストリッパー、香具師、大道芸人を取り上げ、ホモセクシュアルと芸の関係についても考察した。かつて「河原者」「河原乞食」と蔑称で呼ばれていた芸人に思いを寄せ、俳優という生業を問い直そうとする小沢がいた。
これを読んで心を動かされ、レコード化を着想したビクターのプロデューサーがいた。こうして、LPレコード集「ドキュメント 日本の放浪芸」シリーズ全4作が誕生した。
本作は、このドキュメントの意味と制作の舞台裏に学術的に迫ったノンフィクション。著者は近現代日本音楽史を専門とする研究者で、芸と向き合い続けた小沢昭一論も展開している。
1970年代、小沢は、かろうじて残っている放浪芸を求めて全国各地を巡り歩いた。スタジオではなく、芸の現場で生の音を掬い取り、そのありようを自らの言葉で語った。
シリーズ第1作では、「はこまわし」「大黒芸」といった祝う芸、「節談説法」「辻咄」など説く芸、「ごぜ唄」「口寄せ」など目の不自由な人の芸や語る芸という具合に放浪遊行の諸芸が採録されている。滅びゆく声の記録は日本人の琴線に触れたのか、話題を呼び、LPはシリーズ化された。
小沢にとってこの探訪の動機は、日本の芸能者の出身の土壌を確認して、俳優の仕事によりどころを見つけることにあった。
「保存にはあまり関心はございません」と小沢は言う。
この国の芸能は世の「はずれ者」たちが担ってきた。彼らのことを小沢はクロウトと呼ぶ。クロウトにならざるを得なかった人々こそ本物の芸能者と考え、自分のニセモノ性と向き合った。
世間が捨てた芸を集めた「ドキュメント 日本の放浪芸」は、クロウトに対する思慕の情から生まれ、小沢のライフワークとなった。
(春秋社 2750円)