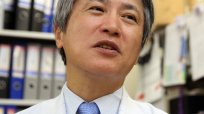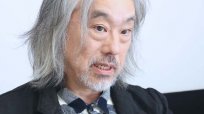「良質な睡眠を得るための食べ方」時間栄養学の第一人者・柴田重信氏が語る
いつ、何を食べるかによって睡眠の質は変わる──。こう言うのは日本の時間栄養学の第一人者で早稲田大学先進理工学部の柴田重信教授だ。2017年のノーベル生理学・医学賞受賞で話題となった体内時計をつかさどる時計遺伝子のメカニズム。地球上の生物が持つ1日約24時間のリズム(サーカディアンリズム)を調節する役割がある体内時計だが、最近の研究で肥満や睡眠など私たちの健康に関わりがあることがわかってきた。そしてこの体内時計の調整に重要な役割を果たしているのが食事だという。柴田教授に「良質な睡眠を得るための食べ方」について聞いた。
◇ ◇ ◇
──そもそも体内時計とは何ですか?
「体内の時間軸を調整するシステムのことをいいます。私たちは本来24時間よりも少し長い1日を刻みますが、体内時計のおかげで24時間周期の毎日を過ごすことができています。体内時計によって私たちは朝目が覚めて、夜眠くなるのですが、そのほかにも朝になると血圧が上がって目覚めの準備がされたり、寝ている間は体温が下がったり、私たちが暮らす24時間の生活に応じて、体の状態が変化しています。ところがこの体内時計が正常に働かないことで、睡眠障害やうつ病、肥満や糖尿病、がんやアレルギーなど、さまざまな疾患につながることがわかっています」
──食事はそれとどう関係しているのですか?
「体内時計は1日24時間より少し長い周期で動いていることがわかっています。これを24時間にリセットするために重要な役割を果たしているのが光と食事の刺激なのです。朝の光の刺激が網膜を通じて脳に伝わることで、脳の中の親時計がリセットされ動き始めます。一方、子時計は光の刺激と共同しながらも食事によって動き出すことがわかっています。つまり、食事をする時間は体調に大きく関わっているということです。それはつまり、同じ人が同じものを食べても、1日のうちにいつ、何を食べたかで太りやすくなったり、痩せやすくなったり、血圧が高くなったり、変わらなかったりという反応が起きるからです」
──時間栄養学はそれを明らかにする学問ということですか?
「その通りです。健康に役立つ食・栄養については、量、質、場所、誰と、などに注目されて研究されてきましたが、『いつ』の要素が欠けていました。しかし、同じ食べ物を食べても朝と夕、平日と週末といった、食・栄養を取るタイミングによって、食が体に果たす役割が変わります。たとえば、ヒトには早起きが得意な朝型、夜更かししても眠くならない夜型、どちらでもない中間型があります。それも時計遺伝子が関係していて、食事の時間や内容によってタイプを変えられることがあります。つまり、朝食、昼食、夕食、おやつといった食行動と、それによって引き起こされる体内の時間帯別の反応との関係を明らかにする学問が時間栄養学なのです。それは睡眠にも大きく関わっています」