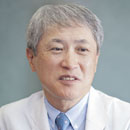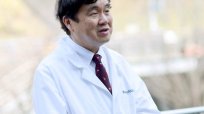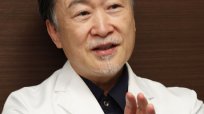夜は照明を消して真っ暗な環境で眠ることが心臓を守る
■長く交感神経が優位になっていると負担大
ところが、夜間に強い光を浴びるなど明るい環境で過ごしていると、交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかなくなってしまいます。夜間になっても自律神経の切り替えが不十分で、交感神経が優位になっている時間が長くなると、先ほど触れたように心拍数が増えたり血圧が上昇している状態が続くことになります。それだけ、心臓の負担が増えたり、動脈硬化が促進され、心臓病リスクがアップしてしまうのです。
一日の睡眠時間が5時間以下の人は心臓病の発症率が上昇し、4時間以下になると冠動脈性心疾患による死亡率が上がったり、就寝中に何度も呼吸が止まる睡眠時無呼吸症候群(SAS)がある人は、狭心症、心筋梗塞、心房細動といった病気が起こりやすいのも同じ理由です。
前述したように、夜間に弱い光を浴びるだけでも心臓病リスクは徐々に高くなり、研究者は夜間に室内で物がはっきりと見えるほどの明るさなら、すでに健康上のリスクが高まっている可能性があると指摘しています。また、米国のノースウエスタン大の研究では、街灯の差し込み光や豆電球程度の明かりでも、睡眠時の呼吸、心拍数、メラトニンの分泌などに影響を与え、睡眠の質を低下させると報告しています。ですから、夜間はなるべく照明の明るさを落とした部屋で過ごし、ベッドではスマホやタブレットを見ないように心掛け、就寝の際は寝室の照明を完全に消して、真っ暗な環境で眠るのが理想的であり、糖尿病・高血圧・肥満などの心臓病リスクをかかえている方はこれを心がけるだけで健康寿命を伸ばすことにつながる可能性もあります。